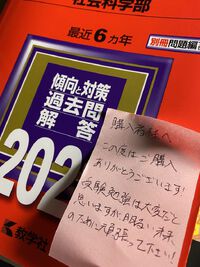2013年02月05日
コーチングと『こころの処方箋』
塾の講師がやるべき仕事として勉強を上手に教えることはもちろんですが、それと同様に大切なことは子供たちからやる気を引き出し、自分自身で考える力と習慣を身につけさせることだと考えます。そのため、どうしたらいいか・・・・。う~ん、たいへんに難しい課題です。毎日試行錯誤です。
そのために心理カウンセリングを勉強しようと、通信講座を受講してほんの小さな資格ですが『チャイルドコーチングアドバイザー』というものを取得しました。講座を通して傾聴、質問の仕方、上手いほめ方叱り方や、型にはめ込まない配慮・・・いろんなノウハウを学ぶことができました。そのことを毎日の授業の教え方に取り入れています。また、暇を見つけてはいろんな心理学の本も読んでいます。(最近は入試対策で中断していますが・・・・。)
今『体罰』という問題が注目されていますが、一連のニュースを聞くたびに、日本のスポーツ界は『巨人の星』の時代と変わってなかったのか?!今の時代『コーチング理論』を履修することはトップ選手の指導にたずさわる人たちには必須ではなかったのか?と少し驚きました・・・。
心理療法の第一人者 故 河合隼雄先生の『こころの処方箋』というの本の中の「耐えるだけが精神力ではない。」というエッセイがあります。
「日本人は精神力(根性論)という言葉が大好きで特にスポーツでもてはやされる。しかし、多くの場合『忍耐力』ばかり強調される。指導者は『耐えること』第一目標に掲げ、選手に体罰含め、しごきが、あたかも愛の鞭であるかのように与える。忍耐力さえあればすべてが上手いくかのようだ。 仮に上手くいかない場合は選手に忍耐力が足りないから・・、もう一回精神を鍛えなおせ!という図式が見られる。しかし本当の精神力はもっと広義な意味で、『想像=創造力』というものがある。『忍耐力』を強要する指導法では、選手の『想像=創造力』をという最も大切な芽を摘みとってしまうのだ。これは何もスポーツに限ったことでなく、教育や仕事・・・日本の指導方に広く見られるのだ。」というような内容がすでに20年以上もまえに書かれていたのです。
たまたま夕べ見たE-TVのスーパープレゼンテーションという番組では、アメリカの企業や団体の調査で、人のモティベーションを上げるには 飴と鞭だけでは上手くいかない。成功報酬をいくら上げても(同時にダメなら首)行き詰る。 イノベーションをもたらす創造性が求められる仕事ではむしろ障害になる。それより無報酬にするかわりに、自由さ、楽しさ、やりがい、面白さ、自主性を与えるほうが結果は良いのだ。とあの弱肉強食社会のお手本のようなアメリカのビジネスの世界でこのような結果がでたと、夕べのプレゼンターは言っていました。スポーツも同様に自立的に創造力を発揮できる選手が忍耐力だけの選手より最終局面ではきっと強いのだと思います。
受験もおなじようなことがいえると思います。試験を受けるのは誰でもない彼・彼女自身であり、ぎりぎりの局面を打開できるのは彼・彼女が自立的に考えることができる力である、と考えます。さらにその力は受験だけでなく、長い目で見て将来いろんなところでいろんな局面でより大きな力を発揮できるのだと考えます。
塾生には自立的に考える力を身につけてほしい・・・と、日々考え、努力・実践をしています。
そのために心理カウンセリングを勉強しようと、通信講座を受講してほんの小さな資格ですが『チャイルドコーチングアドバイザー』というものを取得しました。講座を通して傾聴、質問の仕方、上手いほめ方叱り方や、型にはめ込まない配慮・・・いろんなノウハウを学ぶことができました。そのことを毎日の授業の教え方に取り入れています。また、暇を見つけてはいろんな心理学の本も読んでいます。(最近は入試対策で中断していますが・・・・。)
今『体罰』という問題が注目されていますが、一連のニュースを聞くたびに、日本のスポーツ界は『巨人の星』の時代と変わってなかったのか?!今の時代『コーチング理論』を履修することはトップ選手の指導にたずさわる人たちには必須ではなかったのか?と少し驚きました・・・。
心理療法の第一人者 故 河合隼雄先生の『こころの処方箋』というの本の中の「耐えるだけが精神力ではない。」というエッセイがあります。
「日本人は精神力(根性論)という言葉が大好きで特にスポーツでもてはやされる。しかし、多くの場合『忍耐力』ばかり強調される。指導者は『耐えること』第一目標に掲げ、選手に体罰含め、しごきが、あたかも愛の鞭であるかのように与える。忍耐力さえあればすべてが上手いくかのようだ。 仮に上手くいかない場合は選手に忍耐力が足りないから・・、もう一回精神を鍛えなおせ!という図式が見られる。しかし本当の精神力はもっと広義な意味で、『想像=創造力』というものがある。『忍耐力』を強要する指導法では、選手の『想像=創造力』をという最も大切な芽を摘みとってしまうのだ。これは何もスポーツに限ったことでなく、教育や仕事・・・日本の指導方に広く見られるのだ。」というような内容がすでに20年以上もまえに書かれていたのです。
たまたま夕べ見たE-TVのスーパープレゼンテーションという番組では、アメリカの企業や団体の調査で、人のモティベーションを上げるには 飴と鞭だけでは上手くいかない。成功報酬をいくら上げても(同時にダメなら首)行き詰る。 イノベーションをもたらす創造性が求められる仕事ではむしろ障害になる。それより無報酬にするかわりに、自由さ、楽しさ、やりがい、面白さ、自主性を与えるほうが結果は良いのだ。とあの弱肉強食社会のお手本のようなアメリカのビジネスの世界でこのような結果がでたと、夕べのプレゼンターは言っていました。スポーツも同様に自立的に創造力を発揮できる選手が忍耐力だけの選手より最終局面ではきっと強いのだと思います。

受験もおなじようなことがいえると思います。試験を受けるのは誰でもない彼・彼女自身であり、ぎりぎりの局面を打開できるのは彼・彼女が自立的に考えることができる力である、と考えます。さらにその力は受験だけでなく、長い目で見て将来いろんなところでいろんな局面でより大きな力を発揮できるのだと考えます。
塾生には自立的に考える力を身につけてほしい・・・と、日々考え、努力・実践をしています。