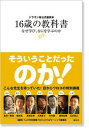2009年08月31日
平成二十一年八月三十一日。
残暑も緩んで、秋の気配を感じますね。
今日で、夏休講座も終わりです・・・。
先週は夏期講座最終週、朝夕晩の追い込み授業の日々でした。
(合間をぬって投票にいきました。)
そして昨日の日曜は、中学生佐賀県一斉模試を当塾で行いました。
今はちょっとホッとしています。

佐賀県立美術館。ricoh Caplio GX100
授業中、課題をもくもくと解いている生徒さんたちを眺めながら、今度の選挙でこの子達の明るい未来を創れる人がより多く当選して欲しいと思っていました。
そして昨日の開票結果、民主党は圧勝し、政権交代を実現しました。それと同時にとてつもない大きな責任を担いました。
新政権には子供たちのために、彼らの将来のためにいい政策を実行して欲しいです。そうしなければならない義務と責任があります。
今日で、夏休講座も終わりです・・・。
先週は夏期講座最終週、朝夕晩の追い込み授業の日々でした。
(合間をぬって投票にいきました。)
そして昨日の日曜は、中学生佐賀県一斉模試を当塾で行いました。
今はちょっとホッとしています。
佐賀県立美術館。ricoh Caplio GX100
授業中、課題をもくもくと解いている生徒さんたちを眺めながら、今度の選挙でこの子達の明るい未来を創れる人がより多く当選して欲しいと思っていました。
そして昨日の開票結果、民主党は圧勝し、政権交代を実現しました。それと同時にとてつもない大きな責任を担いました。
新政権には子供たちのために、彼らの将来のためにいい政策を実行して欲しいです。そうしなければならない義務と責任があります。
2009年08月25日
TOEICで就活
まず朗報!TOEIC受験料値下げされました。
http://www.toeic.or.jp/info/017.html
9月から 旧6,615円(うち消費税等315円)から新価格5,985円(うち消費税等285円)になりました。
さて、今やTOEICのスコア は就活の必須要件ですね。
ココに興味深いデータがあります。
『半数以上の企業が採用時にTOEICのスコアを考慮に入れる。』とあります。期待スコアは400~500だそうです。(英検だとおよそ準2級~2級レベル)しかし外資系や中途採用は、もっともっと高いはずです。また海外部門を持つ会社では就職後も昇格要件としてTOEICのスコアが設定されています。国際化の流れ、今後ますます社員の英語力が重要視されていくことでしょう。
とはいうものの、企業が一番重要視しているのは『コミュニケーション能力』だそうです。(資格ばかりではないと・・・。)

(カメラはナチュラクラシカ使用。現役で販売されてるフィルムカメラです。)
ではTOEICと英検とどうちがうの?
大雑把に言えば、英語試験に対するものが英検が教育的アプローチに対して、TOEICはビジネス的アプローチと言えるかもしれません。TOEICはどちらかというと英文科以外の大学生や一般社会人がより多く受験します。一方、英検は中高生や英文科の学生、帰国子女や教師・講師などが受けている印象があります。
TOEIC試験は社会人向けの実用英語問題です。広告・求人応募・アンケート・メニュウ・価格表・グラフや表などから情報をいかに正確にすばやく読み取るか試されます。熟考を要するような難問はありませんが問題は2時間びっしりの量です。集中力と持続力が要ります。コツはわからないところがあっても割り切ってリズムよくサッサのサで解いていくことです。
いっきゅうはTOEIC対策も致しております!
http://www.toeic.or.jp/info/017.html
9月から 旧6,615円(うち消費税等315円)から新価格5,985円(うち消費税等285円)になりました。
さて、今やTOEICのスコア は就活の必須要件ですね。
ココに興味深いデータがあります。

『半数以上の企業が採用時にTOEICのスコアを考慮に入れる。』とあります。期待スコアは400~500だそうです。(英検だとおよそ準2級~2級レベル)しかし外資系や中途採用は、もっともっと高いはずです。また海外部門を持つ会社では就職後も昇格要件としてTOEICのスコアが設定されています。国際化の流れ、今後ますます社員の英語力が重要視されていくことでしょう。
とはいうものの、企業が一番重要視しているのは『コミュニケーション能力』だそうです。(資格ばかりではないと・・・。)
(カメラはナチュラクラシカ使用。現役で販売されてるフィルムカメラです。)
ではTOEICと英検とどうちがうの?
大雑把に言えば、英語試験に対するものが英検が教育的アプローチに対して、TOEICはビジネス的アプローチと言えるかもしれません。TOEICはどちらかというと英文科以外の大学生や一般社会人がより多く受験します。一方、英検は中高生や英文科の学生、帰国子女や教師・講師などが受けている印象があります。
TOEIC試験は社会人向けの実用英語問題です。広告・求人応募・アンケート・メニュウ・価格表・グラフや表などから情報をいかに正確にすばやく読み取るか試されます。熟考を要するような難問はありませんが問題は2時間びっしりの量です。集中力と持続力が要ります。コツはわからないところがあっても割り切ってリズムよくサッサのサで解いていくことです。
いっきゅうはTOEIC対策も致しております!
2009年08月21日
英語で案内『脇野の大念仏踊り』
8月21日伊万里市東山代町の脇野の宝積寺境内にて 大念仏という念仏踊りの祭事が行われます。
地域の安全と雨乞いと五穀豊穣祈願。独特の回転する踊りが奉納されます。(神社ではないところ面白いですね。)旗竿を中心に8人の白装束の踊り手が太鼓と鉦を鳴らしながらゆっくりゆっくり廻りだします。そしてそのゆったりした優雅な踊りが、次第に回転速度を増してゆくのです・・・。
The festivals I witnessed took place in the evening of August 21st at Houseki-Temple located in Wakinino, northwestern Imari. The Nenbutsu-odori is a unique ritual dance to pray for sufficient rain and a rich harvest. Eight Kimono clad dancers striking bells and drums slowly walk around the flagpoles held by eight seniors. The elegantly slow dancing gradually speeds up in three stages of the Nenbutsu dance routine.

『歴史的背景』
念仏踊りは平安時代の京都で始まりました。空也によって始められたこの踊りは一遍によって全国に広められました。その時代、自然災害が相次ぎ、それは怒れる精霊がもたらしてると信じられてました。その怒れる精霊を鎮めるために、念仏踊りが奉げられました。
ある貴族が政争に敗れて、京都から追放されますが、この地の統領である松浦党の党首によって保護されました。その貴族が京都で行われて念仏踊りをこの地に紹介したのが、脇野の大念仏の原型と言われてます。そして脇野人々はこの伝統ある儀式を今日まで大切に守っています。儀礼的ルールは、演技、衣装、道具、儀式の手順などすべて厳格に守らているそうです。
『Historical Background』
The origin of the Dai-Nenbutsu festival dates back to the Heian period (about 900 years ago) in Kyoto. This festival was started by Kuya, a Buddhist priest, and widely spread across Japan by Ippen priests throughout the Kamakura period. At the time, occurrences of natural disasters were believed to be caused by evil spirits of the dead which harbored grudges in the real world. In order to calm down the angry spirits, the Nenbutsu dance was dedicated to them.
In 1082, Urauchi Awazi-nokami, a noble man who was expelled from Kyoto (the capital of Japan at the time) over a political dispute, was granted asylum by a lord of the Matsura clan. He eventually settled down in the feudal settlement of the Matsura clan located around the Imari Gulf. He brought the rituals performed at Nibu Temple in Kyoto to the feudal settlements in northern Nagasaki around present-day western Saga prefecture. Wakagi villagers in Imari have been faithfully observing the original form of these rituals. In the minds of the villagers, every rule must be stringently followed with respect to musical performances, dance performances, costumes, miscellaneous procedures, and so on.

『儀式』
舞踏4周ぐらいで、精霊が降りてくるのを待ちます。5週目から7週目で、8人の長老の念仏や謡とともにその精霊と踊り手が一体化します。まくりと呼ばれる最後の8週目で、ついに精霊の声を受け取り、その喜びを激しい踊りで表現します。そのちに精霊は再び、自分の世界へ帰っていきます。

『The rituals』
Dancing around in rounds 1-4, accompanied by the sounds of drums and bells, the dancers are conjuring up the spirits. In the 8th rounds,called Makuri ;the dancers express their ecstasy after realizing that their prayers have been answered. Afterwards, they eventually send the spirits off to heaven.
地域の安全と雨乞いと五穀豊穣祈願。独特の回転する踊りが奉納されます。(神社ではないところ面白いですね。)旗竿を中心に8人の白装束の踊り手が太鼓と鉦を鳴らしながらゆっくりゆっくり廻りだします。そしてそのゆったりした優雅な踊りが、次第に回転速度を増してゆくのです・・・。
The festivals I witnessed took place in the evening of August 21st at Houseki-Temple located in Wakinino, northwestern Imari. The Nenbutsu-odori is a unique ritual dance to pray for sufficient rain and a rich harvest. Eight Kimono clad dancers striking bells and drums slowly walk around the flagpoles held by eight seniors. The elegantly slow dancing gradually speeds up in three stages of the Nenbutsu dance routine.

『歴史的背景』
念仏踊りは平安時代の京都で始まりました。空也によって始められたこの踊りは一遍によって全国に広められました。その時代、自然災害が相次ぎ、それは怒れる精霊がもたらしてると信じられてました。その怒れる精霊を鎮めるために、念仏踊りが奉げられました。
ある貴族が政争に敗れて、京都から追放されますが、この地の統領である松浦党の党首によって保護されました。その貴族が京都で行われて念仏踊りをこの地に紹介したのが、脇野の大念仏の原型と言われてます。そして脇野人々はこの伝統ある儀式を今日まで大切に守っています。儀礼的ルールは、演技、衣装、道具、儀式の手順などすべて厳格に守らているそうです。
『Historical Background』
The origin of the Dai-Nenbutsu festival dates back to the Heian period (about 900 years ago) in Kyoto. This festival was started by Kuya, a Buddhist priest, and widely spread across Japan by Ippen priests throughout the Kamakura period. At the time, occurrences of natural disasters were believed to be caused by evil spirits of the dead which harbored grudges in the real world. In order to calm down the angry spirits, the Nenbutsu dance was dedicated to them.
In 1082, Urauchi Awazi-nokami, a noble man who was expelled from Kyoto (the capital of Japan at the time) over a political dispute, was granted asylum by a lord of the Matsura clan. He eventually settled down in the feudal settlement of the Matsura clan located around the Imari Gulf. He brought the rituals performed at Nibu Temple in Kyoto to the feudal settlements in northern Nagasaki around present-day western Saga prefecture. Wakagi villagers in Imari have been faithfully observing the original form of these rituals. In the minds of the villagers, every rule must be stringently followed with respect to musical performances, dance performances, costumes, miscellaneous procedures, and so on.

『儀式』
舞踏4周ぐらいで、精霊が降りてくるのを待ちます。5週目から7週目で、8人の長老の念仏や謡とともにその精霊と踊り手が一体化します。まくりと呼ばれる最後の8週目で、ついに精霊の声を受け取り、その喜びを激しい踊りで表現します。そのちに精霊は再び、自分の世界へ帰っていきます。

『The rituals』
Dancing around in rounds 1-4, accompanied by the sounds of drums and bells, the dancers are conjuring up the spirits. In the 8th rounds,called Makuri ;the dancers express their ecstasy after realizing that their prayers have been answered. Afterwards, they eventually send the spirits off to heaven.
2009年08月19日
前回英検と10月英検。
夏休み宿題、進んでますか?と、ある小学生の生徒さんに聞くと、う~ん、漢字書きとりがまだ~。(>_<) と言ってました。(笑)よくよく考えてみれば漢字はアルファベットよりはるかに複雑な『記号』ですよね。それを覚えていくのですから、たいしたもんですよ。
漢字は象形文字ですね、つまり意味をイメージで覚えられますね。実は英語の単語もその意味をイメージできることが大切です。たとえば、white clouds in the blue sky を見るだけで、その映像がパッと浮かべられるようになれば、定着しているといえるかもしれません。そこで生徒さんは、単語を見てその絵をイメージして、次に、つづりをイメージしてもらいます。もちろん音声も大切ですので、フォニックスと組み合わせて、音読・書き取りを何度も続けます。確認として、つづりをみて映像が浮かぶかどうかがポイントとなります。

閑話休題;‘09度 第二回英検の申し込みがもう始まっています。
1次は10月18日。 2次は11月15日です。
前回は、いつきゅうの生徒さんは 2級 1名(高3)。 5級 1名(中1)。合格されました! (受験する生徒さんがまだまだ少ないです・・・。みなさん英検受けましょう!)
2級合格の高校生は2次面接試験が高得点でした。1対1で模擬面接演習やった成果がでました。一般社会で、英語が特技と見なされるのは英検2級からです。(履歴書の特技・資格に書けます。)また大学入試・推薦や留学にも有利になると。それを高校時代で取得できたのはエライ!です。
5級の中学生は英語はじめてまもなくでしたが、わずか2ヶ月あまりの勉強でよく受かりました。文法的に言えば1年生全部の範囲ですからね。これもエライです。
いっきゅうでは、当塾の生徒さんが英検受験され、級を所得された生徒さんに1レッスン無料にします。また【英検特待生割引】があります。詳しくはココクリックしてください。
成人の方も歓迎です。
成人様向けのとくとく講座です。詳しくはクリックしてください
 。準1級レベルで英字新聞サクサク読めるようになりますよ。
。準1級レベルで英字新聞サクサク読めるようになりますよ。
さぁ頑張りましょう!
漢字は象形文字ですね、つまり意味をイメージで覚えられますね。実は英語の単語もその意味をイメージできることが大切です。たとえば、white clouds in the blue sky を見るだけで、その映像がパッと浮かべられるようになれば、定着しているといえるかもしれません。そこで生徒さんは、単語を見てその絵をイメージして、次に、つづりをイメージしてもらいます。もちろん音声も大切ですので、フォニックスと組み合わせて、音読・書き取りを何度も続けます。確認として、つづりをみて映像が浮かぶかどうかがポイントとなります。
閑話休題;‘09度 第二回英検の申し込みがもう始まっています。
1次は10月18日。 2次は11月15日です。
前回は、いつきゅうの生徒さんは 2級 1名(高3)。 5級 1名(中1)。合格されました! (受験する生徒さんがまだまだ少ないです・・・。みなさん英検受けましょう!)
2級合格の高校生は2次面接試験が高得点でした。1対1で模擬面接演習やった成果がでました。一般社会で、英語が特技と見なされるのは英検2級からです。(履歴書の特技・資格に書けます。)また大学入試・推薦や留学にも有利になると。それを高校時代で取得できたのはエライ!です。
5級の中学生は英語はじめてまもなくでしたが、わずか2ヶ月あまりの勉強でよく受かりました。文法的に言えば1年生全部の範囲ですからね。これもエライです。
いっきゅうでは、当塾の生徒さんが英検受験され、級を所得された生徒さんに1レッスン無料にします。また【英検特待生割引】があります。詳しくはココクリックしてください。

成人の方も歓迎です。
成人様向けのとくとく講座です。詳しくはクリックしてください

 。準1級レベルで英字新聞サクサク読めるようになりますよ。
。準1級レベルで英字新聞サクサク読めるようになりますよ。さぁ頑張りましょう!
2009年08月18日
『英語で浮立案内』
肥前地方(佐賀・長崎)では浮立のお祭りの季節になりました。私は浮立を見るのが大好きです。田舎の小さな村々の鎮守の杜の境内で行われる浮立のお祭りはいかにも日本の村祭りという趣があります。それぞれのお祭りが違う特徴を持ってます。地域の人々が代々大切にしてきた『無形の文化財』をみることは自分の祖先の生活の一部を見るようでとても興味深いです。
一般に浮立というのは肥前地方の伝統的・宗教的踊りで、特徴のある衣装と伝統音楽を伴って行われます。浮立の祭りは村の先祖や神様に、五穀豊穣の祈願と感謝、また災いをもたらす悪霊払いのため奉げられます。その形態は村々によって様々ですが舞踏・衣装・音楽の形式は平安・室町時代に出来上がったそうです。

厳木:広瀬浮立
"Furyu" is a very unique form of traditional and religious folk dancing with unique costumes and instruments. It has a close relationship with religion. Furyu is dedicated to ancestor spirits or deities in each community to pray for rich harvests, sufficient rain, peace, and to ward off evil spirits that are believed to bring plagues and natural disasters. The characteristics of Furyu vary from place to place. Each has its own unique costumes, music and songs developed and influenced by Japanese culture since the Heian and Muromachi periods around the 11th century.
そもそも『浮立・ふりゅう』とは漢字で『風流・ふうりゅう』から来た読み方で、風流の意味としては洒落た、洗練された趣味として文化的な事から人や自然の事柄まで形容します。『風流踊り』は鉦・太鼓・横笛で構成される囃子と呼ばれる音楽とともに行われます。もともとは『盆踊り』から派生してきたとも言われます。さらに盆踊りは『念仏踊り』という仏教の儀礼から来ています。

厳木:広瀬浮立
The word "Furyu" is written with the Chinese characters pronounced as "Fuuryu" in Japanese. In English, "Fuuryu" carries the meaning of "cool" or "chic" with respect to culture, customs, and nature. Sometimes it is called Furyu-Odori, or Furyu dancing. Furyu dance is performed to the music called Hayashi, a unique combination of flutes, drums, and bells. Fuuryu dance has a wide variety of dance forms. Bon dancing is a representative form of Furyu. Bon dance festivals take place in most communities throughout Japan during Bon, the middle of summer. The word "Bon" is a Buddhist erm. People welcome their ancestors' spirits which are believed to come back home from another world during Bon by performing Bon dances and hanginglanterns Nenbutsu Odori (Budhist Invocation Dance)
浮立ついては、これからもいろいろ書いていこうとおもいます。
一般に浮立というのは肥前地方の伝統的・宗教的踊りで、特徴のある衣装と伝統音楽を伴って行われます。浮立の祭りは村の先祖や神様に、五穀豊穣の祈願と感謝、また災いをもたらす悪霊払いのため奉げられます。その形態は村々によって様々ですが舞踏・衣装・音楽の形式は平安・室町時代に出来上がったそうです。

厳木:広瀬浮立
"Furyu" is a very unique form of traditional and religious folk dancing with unique costumes and instruments. It has a close relationship with religion. Furyu is dedicated to ancestor spirits or deities in each community to pray for rich harvests, sufficient rain, peace, and to ward off evil spirits that are believed to bring plagues and natural disasters. The characteristics of Furyu vary from place to place. Each has its own unique costumes, music and songs developed and influenced by Japanese culture since the Heian and Muromachi periods around the 11th century.
そもそも『浮立・ふりゅう』とは漢字で『風流・ふうりゅう』から来た読み方で、風流の意味としては洒落た、洗練された趣味として文化的な事から人や自然の事柄まで形容します。『風流踊り』は鉦・太鼓・横笛で構成される囃子と呼ばれる音楽とともに行われます。もともとは『盆踊り』から派生してきたとも言われます。さらに盆踊りは『念仏踊り』という仏教の儀礼から来ています。

厳木:広瀬浮立
The word "Furyu" is written with the Chinese characters pronounced as "Fuuryu" in Japanese. In English, "Fuuryu" carries the meaning of "cool" or "chic" with respect to culture, customs, and nature. Sometimes it is called Furyu-Odori, or Furyu dancing. Furyu dance is performed to the music called Hayashi, a unique combination of flutes, drums, and bells. Fuuryu dance has a wide variety of dance forms. Bon dancing is a representative form of Furyu. Bon dance festivals take place in most communities throughout Japan during Bon, the middle of summer. The word "Bon" is a Buddhist erm. People welcome their ancestors' spirits which are believed to come back home from another world during Bon by performing Bon dances and hanginglanterns Nenbutsu Odori (Budhist Invocation Dance)
浮立ついては、これからもいろいろ書いていこうとおもいます。
2009年08月16日
『十八夜祭』:英語で案内
有田町(西有田町)大木の 『龍泉寺』で毎年八月十八日に行われる『十八夜祭り』を紹介します。
まさにこれこそ日本の故郷の夏祭り!実に趣のあるお祭りです。浴衣姿の人達が団扇片手にお寺の境内に集まり、浮立に花火・夜店、夏祭りを思い思いに楽しんでられます。(実はこの日は偶然にもワタシの誕生日でもあります。)
The festival on the 18th is held in the evening at Ryusenze Temple and in nearby Nishi-Arita. (Actually, this festival falls on my birthday! I’ve never experienced such a memorable birthday party!) The August 18th festival still follows traditions in terms of its performances and music. Furyu dances and fireworks displays are symbolic forms of prayer for rain and a rich harvest in the present year.
まず、宵の頃、古い家並が残る大木の通りをゆく道行。花火と不思議な伝統音楽と浮立の踊りの行列です。

The procession of Happi (a kind of Kimono) clad people dancing and playing music with flutes, drums and bells, and accompanied by fireworks, creates a mysterious atmosphere along the narrow streets lined with old houses.
そして夜になると出店の並ぶお寺の境内で、若者たちがぶつかり合う儀式がはじまり、道行の行列隊がにぎやかに太鼓と鉦笛の音色を夜空に鳴り響かせながら入場し、浮立踊りがにぎやかに行われます。
Performance; at the opening ceremony of the temple, oddly some youngsters were clashing with each other. According to the local residents, one side was representing the evil spirits who were trying to stop the rituals of the opening ceremony, while the other side was countering them to protect the performers in order that they may continue the rituals of the opening ceremony.
クライマックスは境内に建てられた巨大なジャーモンという仕掛け花火がぐるぐる回り、境内の真上に打ち上げられる花火がお堂とてもいい具合にマッチするのです。
Fireworks; At the climax, “Jamon”, a dragon-like figure, sparks and starts revolving. Behind the sparking Jamon, big rocks start exploding one after another in the sky. It’s an amazing spectacle!
この祭りの歴史的由来は雨乞いの儀式から始まったそうです。むかしは、干ばつが定期的この地域を襲っていたそうです。地元の人によると、この祭りのあと必ず雨が降るそうです。たしかにその翌日から雨の日が続きました。
The Historical Background; According to the historical information about Nishi-Arita provided by the Nishi-Arita town office, a severe drought struck the Arita area in 1532. Ei-tetus, a Buddhist priest, was ordered to pray for rain by a lord who dominated this area. It eventually rained after he had prayed for three days.The lord built Ryusenzi in commemoration of this good fortune. When another drought occurred in Arita in 1658, Sonei, the chief of Ryusenzi, spent 17 days praying for rain by worshiping “the king of dragons” who was believed to manage rain. Also, almost all of the village people performed Furyu dances as a means to pray for rain. Finally, they enjoyed substantial rainfall and even a rich harvest that year.In fact , the local people told me that it has never failed to rain after this festival. The day after the festival, it rained a little indeed. It sounds a little funny, but if it rains heavily, the festival is called off. I think that’s because prayers for rain are no longer necessary.
花火が済んで境内の後して、連れの知人宅に呼ばれました。祭りの期間はこの地域では家を開けて、お客さんをもてなすそうです。そのお宅は浮立で使う笛つくりの達人いらしたそうです。
A local family welcomed us to their house and offered us treats and drinks. They taught us about the background of the festivals and Furyu. In the picture below, flutes for Furyu are featured. The deceased head of the family who was a master flute-player made these flutes. During the days of the festival, visitors are supposed to be welcomed to residents’ houses and wined and dined for free. This custom is called “Bureiko” in Japanese.

今から佐賀・長崎は浮立の季節になりますね。以前は浮立を見るのが好きであちこち見て回ったりもしました。コレカラちょこちょこ英文で案内していこうかと思います。
まさにこれこそ日本の故郷の夏祭り!実に趣のあるお祭りです。浴衣姿の人達が団扇片手にお寺の境内に集まり、浮立に花火・夜店、夏祭りを思い思いに楽しんでられます。(実はこの日は偶然にもワタシの誕生日でもあります。)
The festival on the 18th is held in the evening at Ryusenze Temple and in nearby Nishi-Arita. (Actually, this festival falls on my birthday! I’ve never experienced such a memorable birthday party!) The August 18th festival still follows traditions in terms of its performances and music. Furyu dances and fireworks displays are symbolic forms of prayer for rain and a rich harvest in the present year.
まず、宵の頃、古い家並が残る大木の通りをゆく道行。花火と不思議な伝統音楽と浮立の踊りの行列です。
The procession of Happi (a kind of Kimono) clad people dancing and playing music with flutes, drums and bells, and accompanied by fireworks, creates a mysterious atmosphere along the narrow streets lined with old houses.
そして夜になると出店の並ぶお寺の境内で、若者たちがぶつかり合う儀式がはじまり、道行の行列隊がにぎやかに太鼓と鉦笛の音色を夜空に鳴り響かせながら入場し、浮立踊りがにぎやかに行われます。
Performance; at the opening ceremony of the temple, oddly some youngsters were clashing with each other. According to the local residents, one side was representing the evil spirits who were trying to stop the rituals of the opening ceremony, while the other side was countering them to protect the performers in order that they may continue the rituals of the opening ceremony.
クライマックスは境内に建てられた巨大なジャーモンという仕掛け花火がぐるぐる回り、境内の真上に打ち上げられる花火がお堂とてもいい具合にマッチするのです。
Fireworks; At the climax, “Jamon”, a dragon-like figure, sparks and starts revolving. Behind the sparking Jamon, big rocks start exploding one after another in the sky. It’s an amazing spectacle!
この祭りの歴史的由来は雨乞いの儀式から始まったそうです。むかしは、干ばつが定期的この地域を襲っていたそうです。地元の人によると、この祭りのあと必ず雨が降るそうです。たしかにその翌日から雨の日が続きました。
The Historical Background; According to the historical information about Nishi-Arita provided by the Nishi-Arita town office, a severe drought struck the Arita area in 1532. Ei-tetus, a Buddhist priest, was ordered to pray for rain by a lord who dominated this area. It eventually rained after he had prayed for three days.The lord built Ryusenzi in commemoration of this good fortune. When another drought occurred in Arita in 1658, Sonei, the chief of Ryusenzi, spent 17 days praying for rain by worshiping “the king of dragons” who was believed to manage rain. Also, almost all of the village people performed Furyu dances as a means to pray for rain. Finally, they enjoyed substantial rainfall and even a rich harvest that year.In fact , the local people told me that it has never failed to rain after this festival. The day after the festival, it rained a little indeed. It sounds a little funny, but if it rains heavily, the festival is called off. I think that’s because prayers for rain are no longer necessary.
花火が済んで境内の後して、連れの知人宅に呼ばれました。祭りの期間はこの地域では家を開けて、お客さんをもてなすそうです。そのお宅は浮立で使う笛つくりの達人いらしたそうです。
A local family welcomed us to their house and offered us treats and drinks. They taught us about the background of the festivals and Furyu. In the picture below, flutes for Furyu are featured. The deceased head of the family who was a master flute-player made these flutes. During the days of the festival, visitors are supposed to be welcomed to residents’ houses and wined and dined for free. This custom is called “Bureiko” in Japanese.
今から佐賀・長崎は浮立の季節になりますね。以前は浮立を見るのが好きであちこち見て回ったりもしました。コレカラちょこちょこ英文で案内していこうかと思います。
2009年08月10日
盆休は伊万里なし。
世の中はもう盆休みモードですね。でも、いつきゅうは休みなしです・・。
生徒さんたち来るので。!(^^)!
さて、中学生は面白いです。いろいろと笑わせてくれます。ええ・・・今思い出してみると・・・。
・食器は英語でなに?と訊くと『ショッキィ!』 。
・『先生、オバマ大統領は宇宙人だという説があること知っていますか?』・
・『baseball』のつづりを 『バセバじゅういち』と覚えている・・・。

国見台公園
さぁ、休みなしの盆休み、生徒さんを待ちながらあま~い伊万里梨を楽しもうかな・・。
*家で勉強ヤル気がでないときはいっきゅうで自習もできますよ。自習でも夏休みの課題・なんでも質問していいですよ。
生徒さんたち来るので。!(^^)!
さて、中学生は面白いです。いろいろと笑わせてくれます。ええ・・・今思い出してみると・・・。
・食器は英語でなに?と訊くと『ショッキィ!』 。
・『先生、オバマ大統領は宇宙人だという説があること知っていますか?』・
・『baseball』のつづりを 『バセバじゅういち』と覚えている・・・。

国見台公園
さぁ、休みなしの盆休み、生徒さんを待ちながらあま~い伊万里梨を楽しもうかな・・。
*家で勉強ヤル気がでないときはいっきゅうで自習もできますよ。自習でも夏休みの課題・なんでも質問していいですよ。
2009年08月06日
『キャッチャーインザライ:ライ麦畑でつかまえて』
『蛍雪時代8月号』に夏休みに読むお奨め本が特集されています。テレビでおなじみの心理学者香山リカ先生は(今月号の特別講師)、『キャッチャーインザライ』を推薦されています。一般には『ライ麦畑でつかまえて』という邦題で知られるアメリカの小説です。お奨めの理由として、「高校生の『自分探しの物語』。『自分って何?』といろいろ思っているのは人には、ああ~自分と似たようなことを考えている高校生が昔も(1951年発表)いたんだ~、と知ってホッとする読み物だ」と。
『自分は、広いライ麦畑で遊んでいる子どもたちが、気付かずに崖っぷちから落ちそうになったときに、捕まえてあげるような、そんな人間になりたい。』主人公がたどり着いたひとつの結論です。
私は『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝訳)を大学生のとき読んでとても共感しました。確かに大学時代はワタシも『自分探しの旅』真っ最中だった気がします・・・。今もその旅は終わっていませんが・・・・(笑)。
主人公ホールデングは進学校の落ちこぼれ。でも喧嘩が強いワイルドな不良では決してなく(むしろ弱い。) 鬱陶しく、暗く、ひねくれて、自意識過剰・疎外感をもち・世の中は『嘘(lie)っぱちだらけ』だと思っている、今の日本でも何処にでもいるようなパッとしない青年なのです。(笑)でも、その『語り口』が非常に魅力的なのですね。感受性と言葉の表現力だけはすごくトンがってて、機知に富んで過激な言葉で世の中を切り込んでいきます。この辺をいかに訳するかがこの本の翻訳の醍醐味なのかもしれません。(The Catcher in the Rye 原書も是非読みたいです。)

この作品は『キャッチャーインザライ』というそのままのタイトルで村上春樹によって新しく訳されました。これは未読ですがその翻訳作業については『サリンジャー戦記』という文庫本で翻訳家、柴田元幸さんとの対談で詳しく述べられています。『翻訳』に関心あるワタシにとってもとても興味深い本でした。。

『自分は、広いライ麦畑で遊んでいる子どもたちが、気付かずに崖っぷちから落ちそうになったときに、捕まえてあげるような、そんな人間になりたい。』主人公がたどり着いたひとつの結論です。
私は『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝訳)を大学生のとき読んでとても共感しました。確かに大学時代はワタシも『自分探しの旅』真っ最中だった気がします・・・。今もその旅は終わっていませんが・・・・(笑)。
主人公ホールデングは進学校の落ちこぼれ。でも喧嘩が強いワイルドな不良では決してなく(むしろ弱い。) 鬱陶しく、暗く、ひねくれて、自意識過剰・疎外感をもち・世の中は『嘘(lie)っぱちだらけ』だと思っている、今の日本でも何処にでもいるようなパッとしない青年なのです。(笑)でも、その『語り口』が非常に魅力的なのですね。感受性と言葉の表現力だけはすごくトンがってて、機知に富んで過激な言葉で世の中を切り込んでいきます。この辺をいかに訳するかがこの本の翻訳の醍醐味なのかもしれません。(The Catcher in the Rye 原書も是非読みたいです。)

この作品は『キャッチャーインザライ』というそのままのタイトルで村上春樹によって新しく訳されました。これは未読ですがその翻訳作業については『サリンジャー戦記』という文庫本で翻訳家、柴田元幸さんとの対談で詳しく述べられています。『翻訳』に関心あるワタシにとってもとても興味深い本でした。。

2009年08月04日
『数学という最強の武器と渋滞学』
ドラゴン桜公式副読本『16歳の教科書2』を読んでいます。いろんな分野の第一線で活躍されとても個性的な人が講師となって、16歳へ向けておこなう模擬講座を集めたの本です。その講師のひとり西成活祐(かつひろ)さんの話は抜群におもしろいので、紹介します。
東大の宇宙工学の教授。高校時代、学校で使うテキストは買わず、授業では先生の声がジャマだということで耳栓して独学し(笑)、解けない問題があっても絶対模範解答は見ず、出来るまで一人で考えたと言う・・・。高校の先生にとってはなんとも憎っタラシイ生徒だったことでしょうね。(笑)

彼にとっては中高で教える「数学」は便宜的に「公式」をまる覚えしてパターン化した問題をその公式にそって解いていくものにすぎなかったのかもしれません。いちいち『公式』に対して、なぜなんだ?なぜそうなる?トコトンツッコンで来る生徒に対して『先生たち』はどこまで答えることが出来るのでしょうか?
西成少年の『なぜ?』にこだわった理由。それは『数学という最強の武器を手に入れたかったからだ。』そうです。『数学で証明されたものは、どんな相手だって、大統領だってNOと言えない。』と言う信念があったそうです。(英語に関してはワタシもそんな風にこだわっていたいとおもっています。)
東京大学の先生となった今、西成さんは数学は身近に具体的役に立っていると生徒には教えているそうです。例:ケータイ電話の画像伝送圧縮技術に中学で習う2次関数がつかわれている・・・。また、研究としての『渋滞学』と言うまったくあたらしい分野を開拓されました。
そのひとつの身近な例として『都会では混んでいる電車が来たら、やりすごして次の電車を待つほうが良い。』という法則です。なぜなら、たくさんの乗客が乗せている電車は乗客の乗降のとき時間がかかり遅れがちになるので、次の電車の到着時間の差は短くなる。しかも前の電車が乗客をたくさん乗せていった直後なので混んでない確率が高いし、乗り合わせするひとも少ない。というわけです。エレベータも同様らしいですよ。
『Jカーブ曲線の法則。』 どんな人にも波つまりスランプがある。下り坂をどんどん落っこちていく・・・でもなんとか頑張りぬいて底を抜けると、グーンと上昇する、という法則。目の前のことに一喜一憂することなく長期な視野で努力しているといつか大きな上昇気流が待っているということです。
ドラゴン桜こと桜木先生の招く講師陣の講義集はおもしろいです。当然ながら『16歳の教科書1』もあります。実は1の方が2より面白いと思います。以前読んでまして、ブログに書くつもりが書きそびれちゃったのです。それはいずれまた・・・。
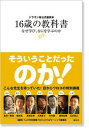
東大の宇宙工学の教授。高校時代、学校で使うテキストは買わず、授業では先生の声がジャマだということで耳栓して独学し(笑)、解けない問題があっても絶対模範解答は見ず、出来るまで一人で考えたと言う・・・。高校の先生にとってはなんとも憎っタラシイ生徒だったことでしょうね。(笑)

彼にとっては中高で教える「数学」は便宜的に「公式」をまる覚えしてパターン化した問題をその公式にそって解いていくものにすぎなかったのかもしれません。いちいち『公式』に対して、なぜなんだ?なぜそうなる?トコトンツッコンで来る生徒に対して『先生たち』はどこまで答えることが出来るのでしょうか?
西成少年の『なぜ?』にこだわった理由。それは『数学という最強の武器を手に入れたかったからだ。』そうです。『数学で証明されたものは、どんな相手だって、大統領だってNOと言えない。』と言う信念があったそうです。(英語に関してはワタシもそんな風にこだわっていたいとおもっています。)
東京大学の先生となった今、西成さんは数学は身近に具体的役に立っていると生徒には教えているそうです。例:ケータイ電話の画像伝送圧縮技術に中学で習う2次関数がつかわれている・・・。また、研究としての『渋滞学』と言うまったくあたらしい分野を開拓されました。
そのひとつの身近な例として『都会では混んでいる電車が来たら、やりすごして次の電車を待つほうが良い。』という法則です。なぜなら、たくさんの乗客が乗せている電車は乗客の乗降のとき時間がかかり遅れがちになるので、次の電車の到着時間の差は短くなる。しかも前の電車が乗客をたくさん乗せていった直後なので混んでない確率が高いし、乗り合わせするひとも少ない。というわけです。エレベータも同様らしいですよ。
『Jカーブ曲線の法則。』 どんな人にも波つまりスランプがある。下り坂をどんどん落っこちていく・・・でもなんとか頑張りぬいて底を抜けると、グーンと上昇する、という法則。目の前のことに一喜一憂することなく長期な視野で努力しているといつか大きな上昇気流が待っているということです。
ドラゴン桜こと桜木先生の招く講師陣の講義集はおもしろいです。当然ながら『16歳の教科書1』もあります。実は1の方が2より面白いと思います。以前読んでまして、ブログに書くつもりが書きそびれちゃったのです。それはいずれまた・・・。