2023年06月10日
@箱崎宮古本市買い物ルポ
こんばんわ!先週の日曜日 箱崎宮 古本市に行ってきました!
只今、独り古本大ブーム真っ最中です。自分にとっては一大イベント。朝はまるで推しアイドルコンサートにいく人のようなワクワク感。

朝.8時30分ごろ出発。
途中、コンビニに寄って、アンパンとーコーヒー。そしてセレクトしたドライブミュージックCD。
(CDプレイヤーで運転、平成っぽいですね。)
姪浜パーキング(ここは安い)に車置いて地下鉄中州で貝塚行に乗り換えて10時40分頃筥崎宮前下車。改札通り、階段上ればそこは箱崎宮参道。11時開始のはずだが案の定、すでにお客さんがたくさん。ざっと全体見渡すと、規模は去年来た時の骨董市の3分の一ほど・・それでも十分の数である。ズタ袋二つ肩にさげて3週周った。 まるで業者だ。(笑)
===========================
@1週目、サクサクまわってめぼしいものを覚えていく。
500円以下でいいものがあれば即決。雑誌類をどんどん買った。
独立系書店さんが多い印象。老舗の古書店というより、個人規模のセレクト古本屋みたいな。故に吾輩好みの少々ニッチなサブカル系アート系本や雑誌がなかなかあった。ただ、学術や希少、初版本、専門書など古書蒐集家や玄人好みの本は少ないようだ。狙いたい本が凡そつかめた。
@2週目
目をつけたお店の単行本をパッパッと買っていく。
お客さんがどんどん増えて手に取るのに一苦労。
買うときに店主さんと交わすちょっとした会話が楽しい。
「これ面白いですよ!」「ハイ!こいうの好きなんで・・・」って感じ。
@3週目
せっかく2時間かけてきたんだから見落としないか再チェックしながらゆっくり回る。追加出品があるかもしれないしネ。3週目となれば気持ちに余裕が出る。(とりあえずめぼしいのは買ったので。)古本市の雰囲気を味合うことにする。本のディスプレイの見せ方、各々個性があって面白い。トランクにいれれてる、リンゴ箱やアンティークなテーブル・・・。店主やお客さんの表情ややりとり見るのも面白い。本を介して本好きの人々の楽しい時間だ。
最後のお店で3冊まとめの(その日初め)値切試みた。コレまとめて500円でどう・・?・と問いかけると「400円でどう?」と来た。「あっハイ!」
「あれ?損しちゃった!」と店主(笑)100円儲かりました!こういうやりとりも市にの楽しさである。
===========================
事務局にチラシをもらって、出店について尋ねた。
出店晴はだれでも応募でできるそうだ。出店も楽しそうだ。
でも車で乗り付けて本を並べて撤収してと考えると丸々1日仕事・・ガソリン代や駐車料・労力考えると採算度外視ですね。
でも楽しそうだ!!
===========================

ズタ袋に本がいっぱい。
経年ヤケの「古井由吉 杳子」いい味出してます。何十年前に文庫本で読んだ。自称文学青年でした(笑)

あれやこれやもっと買えばよかったと、今振り返っているところです。
積読本がまた増えた。(笑)
2023年03月05日
「理想の勉強部屋って何だろう?」
おはようございます。朝5時起きて勉強しておりました。今週ある高校大学入試の仕込みです。で、気づいたこと。高校入試の英語の長文表現は
内容・表現において、大学入試の自由作文に使える!ということ。学生にとってこのレベルの英文英作はとてもやりやすくて使えると思います。
さて、「長時間心地よく勉強していられる部屋。ずっと落ち着いて集中できる部屋」ってどういうものだろう?。
吾輩も狭いながらも書斎で勉強しています。ほぼ毎日です。そして頻繁に模様替えしています。それは言い換えればどうすれば勉強に集中できる理想の環境をつくるための試行錯誤とも言えます。ミニマリストになり切れない(断捨離できない)。ガラクタ・本だらけの趣味部屋をどう変えるのか?
人はf/1揺らぎの灯りやノイズ、揺れ、に癒されるそうです。五感にうれしい波=ゆらぎです。
まず灯りとしての照明。
間接照明部屋を薄暗くしてデスクにはスタンドライト。
これで、いらないモノが視界から消えて集中できます。

ダクレールからのスポットライト型
天井吊り下げのペンダントライト。
あるいは足の長いスタンドライト・・・。
電球もいろいろ。
暖色の強すぎない灯りを複数がよろしいかと、とある動画で照明デザイナーが言っておりました。
次は揺れとしての椅子かな?
デザインも重要ですが機能的に優れた事務用椅子がいいとおもう。
少々お値段はしますが、一番の負担を軽減するモノ。
デスクの予算を削っても椅子はいいものがいいと思う。
恐縮ながら、いっきゅうの椅子は業務用事務器のコンピュータチェアです!
椅子では他の塾屋さんには負けませぬ!!(笑)
揺らぐノイズとしての音楽は
無音派?
音楽必須派?
どちらでもいいのでは?いい気持ちで勉強できれば・・。
ただイヤホンで大音量で聴き続けるのは、耳にも脳にも良いことはないとおもう。
吾輩は唄のないインスト。静かな映画音楽やハラカミレイやブライアンイーノなどの電子環境音楽をかけながらだと気持ちが軽く感じられる。
youtube などでは、小川のせせらぎ、小鳥のさえずり、波や 雨、焚火の音が流れたりもします。
観葉植物も酸素を出してくれてよさそうです。そばに緑にあるだけで癒されます。ただ虫に注意ですね。家は日当たりが悪いので耐陰性が高いものを探してます。多肉でいいものないかと・・。何度か失敗してます。冬が越せないのがいくつか・・。なぜか日光が好きなサボテンは元気です!手もかからなくて丈夫です!とにかく植物はいろいろ勉強中です。
ネット環境遮断しよう!
吾輩の書斎にネットは来てません。勉強中はスマホは書斎に置きません。キッチンです。40分置きぐらいにチェックします。
とにもかくにもネットが最大の敵です!!塾生にも口酸っぱく言っております!!!
ナニナニ?ネットはで調べものができるって??ネットでは教育系のいい動画ありますよって??
知ってるよ!!(笑)でも、それは別の部屋でやってください!!繰り返し言います。ネットが一番の勉強の敵です!!
「香り・匂い」
youtube でルームツアー見るのが好きで(ネットはダメだといいう割に、ネット動画はキッチンや寝室でよく見てます。)
そこでは、比較的若い人のこだわりの部屋を案内されてます。みんなオシャレでカッコイイ部屋ばかりで見とれています。
意外に香やアロマを焚いてる人が多くて・・・・。これも勉強です。
「アート作品」
一般にシンプルな部屋がいいとは思うけど、殺風景なものもねえ・・好きな作家のアート作品を一つ二つ飾るのも部屋にいるのが楽しく心地よくなるのでは?
といわけで、いろいろ考えているであります。
内容・表現において、大学入試の自由作文に使える!ということ。学生にとってこのレベルの英文英作はとてもやりやすくて使えると思います。
さて、「長時間心地よく勉強していられる部屋。ずっと落ち着いて集中できる部屋」ってどういうものだろう?。
吾輩も狭いながらも書斎で勉強しています。ほぼ毎日です。そして頻繁に模様替えしています。それは言い換えればどうすれば勉強に集中できる理想の環境をつくるための試行錯誤とも言えます。ミニマリストになり切れない(断捨離できない)。ガラクタ・本だらけの趣味部屋をどう変えるのか?
人はf/1揺らぎの灯りやノイズ、揺れ、に癒されるそうです。五感にうれしい波=ゆらぎです。
まず灯りとしての照明。
間接照明部屋を薄暗くしてデスクにはスタンドライト。
これで、いらないモノが視界から消えて集中できます。

ダクレールからのスポットライト型
天井吊り下げのペンダントライト。
あるいは足の長いスタンドライト・・・。
電球もいろいろ。
暖色の強すぎない灯りを複数がよろしいかと、とある動画で照明デザイナーが言っておりました。
次は揺れとしての椅子かな?
デザインも重要ですが機能的に優れた事務用椅子がいいとおもう。
少々お値段はしますが、一番の負担を軽減するモノ。
デスクの予算を削っても椅子はいいものがいいと思う。
恐縮ながら、いっきゅうの椅子は業務用事務器のコンピュータチェアです!
椅子では他の塾屋さんには負けませぬ!!(笑)
揺らぐノイズとしての音楽は
無音派?
音楽必須派?
どちらでもいいのでは?いい気持ちで勉強できれば・・。
ただイヤホンで大音量で聴き続けるのは、耳にも脳にも良いことはないとおもう。
吾輩は唄のないインスト。静かな映画音楽やハラカミレイやブライアンイーノなどの電子環境音楽をかけながらだと気持ちが軽く感じられる。
youtube などでは、小川のせせらぎ、小鳥のさえずり、波や 雨、焚火の音が流れたりもします。
観葉植物も酸素を出してくれてよさそうです。そばに緑にあるだけで癒されます。ただ虫に注意ですね。家は日当たりが悪いので耐陰性が高いものを探してます。多肉でいいものないかと・・。何度か失敗してます。冬が越せないのがいくつか・・。なぜか日光が好きなサボテンは元気です!手もかからなくて丈夫です!とにかく植物はいろいろ勉強中です。
ネット環境遮断しよう!
吾輩の書斎にネットは来てません。勉強中はスマホは書斎に置きません。キッチンです。40分置きぐらいにチェックします。
とにもかくにもネットが最大の敵です!!塾生にも口酸っぱく言っております!!!
ナニナニ?ネットはで調べものができるって??ネットでは教育系のいい動画ありますよって??
知ってるよ!!(笑)でも、それは別の部屋でやってください!!繰り返し言います。ネットが一番の勉強の敵です!!
「香り・匂い」
youtube でルームツアー見るのが好きで(ネットはダメだといいう割に、ネット動画はキッチンや寝室でよく見てます。)
そこでは、比較的若い人のこだわりの部屋を案内されてます。みんなオシャレでカッコイイ部屋ばかりで見とれています。
意外に香やアロマを焚いてる人が多くて・・・・。これも勉強です。
「アート作品」
一般にシンプルな部屋がいいとは思うけど、殺風景なものもねえ・・好きな作家のアート作品を一つ二つ飾るのも部屋にいるのが楽しく心地よくなるのでは?
といわけで、いろいろ考えているであります。
2020年04月26日
断捨離ができない。
こんにちわ。今日は日曜日ですね。曜日の感覚がわからなくなります。
今日は昼過ぎから部屋の片づけをしました。吾輩の書斎の様な部屋は景気のいい頃、いろんなものを集めていたもので所狭しの状態です。今回のコロナ問題で考えさせられることがあってほとんどのもが無価値に思えてきたのです。そこで断捨離しようかと思いました。コロナ不況も考えて、この休み期間にすこしづつでもとネットに出品しようかと、処分するものと、取っておくものを仕分けしするつもりが、だんだん愛着というものがよみがえりまして惜しくなってしまいました。 人さまから見れば大したものはないガラクタたちなのですが、個人的にいったんは恋に落ちて手に入れたものたちなのでして・・・・本などは座り込んで読んでしまう始末です。
人さまから見れば大したものはないガラクタたちなのですが、個人的にいったんは恋に落ちて手に入れたものたちなのでして・・・・本などは座り込んで読んでしまう始末です。
そもそも断捨離ってヨガの思想らしいんですが(いわゆる無心・無我の境地に至ることだとおもいますが・・)いらなくなったらといってそれをいくらかのお金に代えようとしたり、結局惜しくて手放せないような物欲に支配されている吾輩は、邪道ですね。断捨離修行というものがあったら即、破門ですかね。修行が足りませぬ。






こういうものがありまして・・・・
ではまた~。
今日は昼過ぎから部屋の片づけをしました。吾輩の書斎の様な部屋は景気のいい頃、いろんなものを集めていたもので所狭しの状態です。今回のコロナ問題で考えさせられることがあってほとんどのもが無価値に思えてきたのです。そこで断捨離しようかと思いました。コロナ不況も考えて、この休み期間にすこしづつでもとネットに出品しようかと、処分するものと、取っておくものを仕分けしするつもりが、だんだん愛着というものがよみがえりまして惜しくなってしまいました。
 人さまから見れば大したものはないガラクタたちなのですが、個人的にいったんは恋に落ちて手に入れたものたちなのでして・・・・本などは座り込んで読んでしまう始末です。
人さまから見れば大したものはないガラクタたちなのですが、個人的にいったんは恋に落ちて手に入れたものたちなのでして・・・・本などは座り込んで読んでしまう始末です。そもそも断捨離ってヨガの思想らしいんですが(いわゆる無心・無我の境地に至ることだとおもいますが・・)いらなくなったらといってそれをいくらかのお金に代えようとしたり、結局惜しくて手放せないような物欲に支配されている吾輩は、邪道ですね。断捨離修行というものがあったら即、破門ですかね。修行が足りませぬ。

こういうものがありまして・・・・

ではまた~。
2018年04月21日
英語マニア
「マイブーム」仕掛け人、みうらじゅんさんのマイブームのひとつに、文具店に売ってあるような英語表示の紙袋を収集する。というものがあるそうだ。(タモリ倶楽部)
なぜ、その英語がそこに印刷されなければならないのか?どうしても気になってマニアックに集めているらしい。たとえば英単語「HOLIZON」よくありがちな英語だ。ではなぜこの袋に「HOLIZON」なのか!?という疑問。番組で製造元にたずねると、ただのデザインらしい。なぜその単語を選らんだの特別な理由はないそうだ。
町にはいろんな英語があふれかえっている。なかにはヘンテコなものある。そういえば、塾生の着たシャツにもおかしな英語がプリントしてあるのが見かけることがある・・。それがどういうものかは忘れてしまったけど・・・。メモしとけばよかった。
で、ちょっと前に撮った写真で洒落たものがあったのでここに紹介します。


【If You're Happy and You Know it Clap Your Hands 】
アメリカの有名なこどもの唄「幸せなら手をたたこう」
よく子供英会話で使われてるようですが、日本では坂本九のカヴァー曲で有名。
写真は町の洋装店にディスプレイされていた。
身の周りのおもしろ英語をマニアックにさがすのも楽しいかも。
追記:最近買った英語の古本です。

息抜きに読んでいます。
なぜ、その英語がそこに印刷されなければならないのか?どうしても気になってマニアックに集めているらしい。たとえば英単語「HOLIZON」よくありがちな英語だ。ではなぜこの袋に「HOLIZON」なのか!?という疑問。番組で製造元にたずねると、ただのデザインらしい。なぜその単語を選らんだの特別な理由はないそうだ。
町にはいろんな英語があふれかえっている。なかにはヘンテコなものある。そういえば、塾生の着たシャツにもおかしな英語がプリントしてあるのが見かけることがある・・。それがどういうものかは忘れてしまったけど・・・。メモしとけばよかった。
で、ちょっと前に撮った写真で洒落たものがあったのでここに紹介します。


【If You're Happy and You Know it Clap Your Hands 】
アメリカの有名なこどもの唄「幸せなら手をたたこう」
よく子供英会話で使われてるようですが、日本では坂本九のカヴァー曲で有名。
写真は町の洋装店にディスプレイされていた。
身の周りのおもしろ英語をマニアックにさがすのも楽しいかも。
追記:最近買った英語の古本です。
息抜きに読んでいます。

2015年04月20日
道草と日本語
大学生の頃、明治の文学を夢中で読んでた時期がある。
夏目漱石、森鴎外、樋口一葉、泉鏡花 ・・文章が凛としている。文字の連なりが音楽的で、視覚的にも美しい。読んだ後、背筋がピンと伸びたような気になっていた。つまり文体に品格があるのだ。
漱石の『道草』の一文 「御前は必竟何をしに世の中に生れて来たのだ」 胸にドスンと来る表現だ。

日本語の特徴は漢字かな混じりにある。表音文字と象形文字で名詞 ・動詞・形容詞・副詞などそれ自体意味の有るものを漢字にして、意味のない助詞などはひらがなにする。そうすることでバランスが取れて、ずいぶん読みやすくなる。 (ひらがなや漢字ばかりの文章ほど読みにくいものはない。) さらに用途に応じてカタカナまである。しかもニュアンスによって漢字ひらがなカタカナは自由に組み替えられるのだ。表意文字である漢字ばかりの中国語や表音文字の英語に比べなんと機能的なんだろう・・・。このような表記システムを持った言語って他にあるのだろうか?それは明治期の言文一致運動によって確立されたのだろう。

明治期は口語と文語が一致しておらず、漢文や文語体と口語のハイブリットの実験過程である。それ故に言葉に対する緊張感を感じる。そして出来上がった明治期の文体には品格を備わっているのだ。
最近の日本語はもう出来上がり過ぎてたせいなのか、平板で緊張感がなく、そういう魅力が薄れてるような気もしないではない。

再び『道草』 漱石自らからの実体験を小説にしたといわれる。
「世の中に片付くなんてものは殆どない」なんて凄みのある台詞だ。
夏目漱石、森鴎外、樋口一葉、泉鏡花 ・・文章が凛としている。文字の連なりが音楽的で、視覚的にも美しい。読んだ後、背筋がピンと伸びたような気になっていた。つまり文体に品格があるのだ。
漱石の『道草』の一文 「御前は必竟何をしに世の中に生れて来たのだ」 胸にドスンと来る表現だ。

日本語の特徴は漢字かな混じりにある。表音文字と象形文字で名詞 ・動詞・形容詞・副詞などそれ自体意味の有るものを漢字にして、意味のない助詞などはひらがなにする。そうすることでバランスが取れて、ずいぶん読みやすくなる。 (ひらがなや漢字ばかりの文章ほど読みにくいものはない。) さらに用途に応じてカタカナまである。しかもニュアンスによって漢字ひらがなカタカナは自由に組み替えられるのだ。表意文字である漢字ばかりの中国語や表音文字の英語に比べなんと機能的なんだろう・・・。このような表記システムを持った言語って他にあるのだろうか?それは明治期の言文一致運動によって確立されたのだろう。

明治期は口語と文語が一致しておらず、漢文や文語体と口語のハイブリットの実験過程である。それ故に言葉に対する緊張感を感じる。そして出来上がった明治期の文体には品格を備わっているのだ。
最近の日本語はもう出来上がり過ぎてたせいなのか、平板で緊張感がなく、そういう魅力が薄れてるような気もしないではない。

再び『道草』 漱石自らからの実体験を小説にしたといわれる。
「世の中に片付くなんてものは殆どない」なんて凄みのある台詞だ。
2015年03月27日
英語で映画【Lost in Translation】の巻
こんにちは。
受験シーズンも終わって映画でもゆっくり見たいとおもうのですが、なかなかそうも行きませぬ。とういわけで、ちょっと昔、北天神の小さな映画館で見た大好きな映画の紹介を『セルフ トランスレーション』してみました。
その映画とは 『ロスト・イン・トランスレーション』 ソフィア・コッポラ監督 2003年 ビル マーレイ・スカーレット ヨハンセン主演。 繊細で美しい映画です。東京が舞台です。言葉通じない 知り合いもいない、文化も違う、 不案内な異国の大都会で 浮遊するような孤独なアメリカ人の成熟した大人の二人男女が出会い、別れる、淡くせつない、恋物語です。
『異文化体験』という言葉がありますが、知り会いも誰もおらず文化がまったく違う場所にたったひとり身を置くこと。この映画のタイトルどおり、言葉も、ココロも身体も置き場が定まらなず、自分自身が喪失していくような感覚・・。 しかし、この孤独感があってこそはじめて『彼・彼女』は失いかけていた生きる事の意味を取り戻していくような希望を得るのだと思います。
This is quite a sensitive and delicate movie. The story is that of the romance between a middle-aged man, Bill Murray, and a young married woman, Scarlet Johansson. It is unique in that it is unlike other love stories; the couple only kisses each other a few times. But this is not a platonic love. The main theme of the story is whether or not sexual relationships between middle-aged men and beautiful young married women are possible. Many of the scenes are sexually suggestive, but decent. They contribute to the movie’s mysterious ending.
The title, Lost in Translation, is quite appropriate. Both of the main characters seem to be tired and lost at this stage of their lives. As they are feeling cut off and lonely in an unfamiliar big city, they meet and gradually become more intimate with each other.
Actually, the main characters were lost in translation as strangers in a different culture. Bill, a famous American actor whose career is going downhill, has come to Japan to appear in a Japanese commercial. During the shooting of the commercial, the Japanese director shouts and gives many instructions to Bill in Japanese and strange English. He makes comments like this: Hey! Hey! Hey! More passion! More gorgeous, more elegant! Please! Please, please! More rich and more and more!? Unfortunately for the director, Bill is at a complete loss.
There is another example in the movie of this sense of being lost in translation. Scarlet injures her toes, so she and Bill go to a hospital. They are given assistance and the results of Starlet’s diagnosis. But the Japanese used only Japanese as if Bill and Scarlet were Japanese. It seemed that they did not care whether or not they were foreigners. I also fine similar scenes at video rental shops. The clerks use only Japanese to explain things to non-Japanese customers. The explanations they give to non-Japanese customers are exactly the same as those given to Japanese customers. The foreigners sometimes nod embarrassingly, but they seem not to have been able to understand any of the Japanese. It’s really amazing that they could succeed in becoming members and rent videos!
One more impressive episode is that of when Scarlet asked Bill why Japanese can’t pronounce L and R accurately. Actually, there was another funny episode involving the words rip and lip. A Japanese prostitute, who suddenly visited Bill’s hotel room, said to Bill, I’m a gift for you from your Japanese agent. Now, lip me my stocking. Come on! Lip! Lip! Lip me!!? Bill was wondering, Lip? What? Why?? Actually, she should have said? rip!. So, Bill responded to her question. The film’s writers must be making fun of Japanese. They must enjoy this. Oh, I should not reveal more details. I won’t tell many things to you if you haven’t seen it.
There are a lot of typical Japanese street scenes. I thought these scenes are typical of what foreigners see. After seeing the movie, I was hovering around like a stranger in the neon-glittering downtown of Fukuoka, which is one of Japan’s big cities. Like Tokyo, the city was also very noisy and glaring. I had the feeling of crowded solitude, but I didn’t dislike.
日本の文化を外国人からエキゾチックに捕らえた映像は可笑しくも、奇妙に美しいものでありました。
エンドロールに流れる曲は我が心のマエストロミュージシャン 細野晴臣+松本 隆の名曲 『風をあつめて』です。

受験シーズンも終わって映画でもゆっくり見たいとおもうのですが、なかなかそうも行きませぬ。とういわけで、ちょっと昔、北天神の小さな映画館で見た大好きな映画の紹介を『セルフ トランスレーション』してみました。
その映画とは 『ロスト・イン・トランスレーション』 ソフィア・コッポラ監督 2003年 ビル マーレイ・スカーレット ヨハンセン主演。 繊細で美しい映画です。東京が舞台です。言葉通じない 知り合いもいない、文化も違う、 不案内な異国の大都会で 浮遊するような孤独なアメリカ人の成熟した大人の二人男女が出会い、別れる、淡くせつない、恋物語です。
『異文化体験』という言葉がありますが、知り会いも誰もおらず文化がまったく違う場所にたったひとり身を置くこと。この映画のタイトルどおり、言葉も、ココロも身体も置き場が定まらなず、自分自身が喪失していくような感覚・・。 しかし、この孤独感があってこそはじめて『彼・彼女』は失いかけていた生きる事の意味を取り戻していくような希望を得るのだと思います。
This is quite a sensitive and delicate movie. The story is that of the romance between a middle-aged man, Bill Murray, and a young married woman, Scarlet Johansson. It is unique in that it is unlike other love stories; the couple only kisses each other a few times. But this is not a platonic love. The main theme of the story is whether or not sexual relationships between middle-aged men and beautiful young married women are possible. Many of the scenes are sexually suggestive, but decent. They contribute to the movie’s mysterious ending.
The title, Lost in Translation, is quite appropriate. Both of the main characters seem to be tired and lost at this stage of their lives. As they are feeling cut off and lonely in an unfamiliar big city, they meet and gradually become more intimate with each other.
Actually, the main characters were lost in translation as strangers in a different culture. Bill, a famous American actor whose career is going downhill, has come to Japan to appear in a Japanese commercial. During the shooting of the commercial, the Japanese director shouts and gives many instructions to Bill in Japanese and strange English. He makes comments like this: Hey! Hey! Hey! More passion! More gorgeous, more elegant! Please! Please, please! More rich and more and more!? Unfortunately for the director, Bill is at a complete loss.
There is another example in the movie of this sense of being lost in translation. Scarlet injures her toes, so she and Bill go to a hospital. They are given assistance and the results of Starlet’s diagnosis. But the Japanese used only Japanese as if Bill and Scarlet were Japanese. It seemed that they did not care whether or not they were foreigners. I also fine similar scenes at video rental shops. The clerks use only Japanese to explain things to non-Japanese customers. The explanations they give to non-Japanese customers are exactly the same as those given to Japanese customers. The foreigners sometimes nod embarrassingly, but they seem not to have been able to understand any of the Japanese. It’s really amazing that they could succeed in becoming members and rent videos!
One more impressive episode is that of when Scarlet asked Bill why Japanese can’t pronounce L and R accurately. Actually, there was another funny episode involving the words rip and lip. A Japanese prostitute, who suddenly visited Bill’s hotel room, said to Bill, I’m a gift for you from your Japanese agent. Now, lip me my stocking. Come on! Lip! Lip! Lip me!!? Bill was wondering, Lip? What? Why?? Actually, she should have said? rip!. So, Bill responded to her question. The film’s writers must be making fun of Japanese. They must enjoy this. Oh, I should not reveal more details. I won’t tell many things to you if you haven’t seen it.
There are a lot of typical Japanese street scenes. I thought these scenes are typical of what foreigners see. After seeing the movie, I was hovering around like a stranger in the neon-glittering downtown of Fukuoka, which is one of Japan’s big cities. Like Tokyo, the city was also very noisy and glaring. I had the feeling of crowded solitude, but I didn’t dislike.
日本の文化を外国人からエキゾチックに捕らえた映像は可笑しくも、奇妙に美しいものでありました。
エンドロールに流れる曲は我が心のマエストロミュージシャン 細野晴臣+松本 隆の名曲 『風をあつめて』です。
2014年01月02日
初授業と今年の新しくやりたいこと。
あけましておめでとうございます。去年の年末は冬季講座やらなんやらで、すっかりご無沙汰でした。書きたいことはそれこそ日々3回づつ更新したいぐらいあるのですが、その日のうちに書かないと忘れてしまいます。そうやってサボりだすと、もうブログのことも忘却の彼方に行ってしまいます。今日は朝から初授業でした。2日の朝からの授業・・・新鮮で気持ちの良いものでした。
さて、本年、新しくやりたいこと。
ひとつめ。『中学五教科』を教えることです。『理科ムズイ・・・』と言う声が多かったのが動機です。もうすでに希望者には理科を不定期に教えてます。春ごろには理科の本格授業を行うつもりです。『社会科』もできれば夏休みぐらいに出来たらとおもってます・・でもまずは要望の多い『理科』です。というわけで短い正月休み(明日からもう講習です。)は理科と受験英数国の対策準備に追われてます。
でもまあ、ほかの塾さんから見れば五教科対応?そんなこと当たり前でしょ?といわれるかもしれませんが、当塾は英語専門塾から始まったのです。大人から小学生までの、英会話、英検、TOEIC,たまにTOEFそして大学、高校の受験英語を専門に教えてるうちに数学の要望が多かったので中学高校生向けの英数専門塾になり、そしてやはり国語は大事でしょ。というわけで中学生には国語。そして、この春に要望の多かった理科が加わり、そしてオオトリのみんな大好き?! でもないか・・社会科もやります。・・というわけで中学五教科も今年は教えたいのです。(で?だからなに?と言われるかもしれませんが・・)これがいっきゅうのささやかな歴史です。特に季節講座や定期試験の対策で理・社も力を入れていきたいです。現役学生のときより勉強してます。ああ、あの時もっとやっとけば・・・反面教師の塾講師です。
次にやりたいことは、『IQ文庫』開設です。すでに小さな文庫は自主学習室にあったのですが、別室に独立させます。私のお気に入りの本ばかりを並べます。とくに絵本・洋書絵本は充実させます。いわば『絵本のセレクトショップ』です。以前このブログも書きましたが絵本はおとなにもお勧めです。というか、絵本はおとなこそ読むべきなのでは?と思ってるぐらいです。映画や小説と違って時間もとられないし・・・こころの滋養になりますよ。かくいう私もストレスがたまるこの受験の季節にたまに絵本を開くとこころがすっーが軽くなります。並べるものはおとなが十分楽しめるものばかりです。私はもともとアート好きだったので『絵=芸術性を重視』して選んでます。絵本美術館とまではいきませんが『無料コーヒーがたまに出るかもしれないブックカフェ風』目指したいです。
絵本のほかは、アート系、サブカル系、旅、雑貨、エッセイ等々・・・。内容もさることながら、その本そのものが、すぐそばにおいて置きたくなるようなものを集めてるつもりです。(なんだか電子書籍の時代に正反対のことをしてますね。) さらに、本の周りには癒し系リヤドロ、ブライスあるいは国内外の無名の手作り民芸人形を展示します。また和洋アンティークな小物、ヴィンテージな北欧雑貨類も少々ですが置いていくつもりです。どこかなつかしく温もりのある雰囲気でくつろげる空間を提供できたら、と考えてます。
音楽も充実です。30年以上も前のレコードプレイヤーとスピーカーですが音がすごく良いです。IPODや WALKMANとの相性も抜群ですので昔から最新のいい音楽(特に映画音楽)いい音が聴けますよ。
春休みぐらいをめどにオープンするつもりです。建具系はおむねできました。あとは陳列です。この準備はすごく楽しみなのですが、今から受験まで3月中旬ぐらいまで何も出来ないと思います。受験が落ち着けば、展示しながら絵本史、国内外の絵本作家・作品論を自分なりに研究しようと思っています・・・。営業時間は正午前ぐらいから、塾が始まる5時前ぐらいに閉店します。それからは塾生ら(ちょっとした休憩場所)と送迎の親御さんに開放します。
ああ・・・たくさん書き過ぎましたね。今後はIQ文庫について詳しくはこのリンク先に書いていこうと存じます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。では、次回までごきげんよう!!
細野晴臣さんの『はらいそ』アニメはさくらももこさん。
どこか不思議な懐かしさと無国籍な異国情緒。こんな感じもいいよな・・。
さて、本年、新しくやりたいこと。
ひとつめ。『中学五教科』を教えることです。『理科ムズイ・・・』と言う声が多かったのが動機です。もうすでに希望者には理科を不定期に教えてます。春ごろには理科の本格授業を行うつもりです。『社会科』もできれば夏休みぐらいに出来たらとおもってます・・でもまずは要望の多い『理科』です。というわけで短い正月休み(明日からもう講習です。)は理科と受験英数国の対策準備に追われてます。
でもまあ、ほかの塾さんから見れば五教科対応?そんなこと当たり前でしょ?といわれるかもしれませんが、当塾は英語専門塾から始まったのです。大人から小学生までの、英会話、英検、TOEIC,たまにTOEFそして大学、高校の受験英語を専門に教えてるうちに数学の要望が多かったので中学高校生向けの英数専門塾になり、そしてやはり国語は大事でしょ。というわけで中学生には国語。そして、この春に要望の多かった理科が加わり、そしてオオトリのみんな大好き?! でもないか・・社会科もやります。・・というわけで中学五教科も今年は教えたいのです。(で?だからなに?と言われるかもしれませんが・・)これがいっきゅうのささやかな歴史です。特に季節講座や定期試験の対策で理・社も力を入れていきたいです。現役学生のときより勉強してます。ああ、あの時もっとやっとけば・・・反面教師の塾講師です。
次にやりたいことは、『IQ文庫』開設です。すでに小さな文庫は自主学習室にあったのですが、別室に独立させます。私のお気に入りの本ばかりを並べます。とくに絵本・洋書絵本は充実させます。いわば『絵本のセレクトショップ』です。以前このブログも書きましたが絵本はおとなにもお勧めです。というか、絵本はおとなこそ読むべきなのでは?と思ってるぐらいです。映画や小説と違って時間もとられないし・・・こころの滋養になりますよ。かくいう私もストレスがたまるこの受験の季節にたまに絵本を開くとこころがすっーが軽くなります。並べるものはおとなが十分楽しめるものばかりです。私はもともとアート好きだったので『絵=芸術性を重視』して選んでます。絵本美術館とまではいきませんが『無料コーヒーがたまに出るかもしれないブックカフェ風』目指したいです。
絵本のほかは、アート系、サブカル系、旅、雑貨、エッセイ等々・・・。内容もさることながら、その本そのものが、すぐそばにおいて置きたくなるようなものを集めてるつもりです。(なんだか電子書籍の時代に正反対のことをしてますね。) さらに、本の周りには癒し系リヤドロ、ブライスあるいは国内外の無名の手作り民芸人形を展示します。また和洋アンティークな小物、ヴィンテージな北欧雑貨類も少々ですが置いていくつもりです。どこかなつかしく温もりのある雰囲気でくつろげる空間を提供できたら、と考えてます。
音楽も充実です。30年以上も前のレコードプレイヤーとスピーカーですが音がすごく良いです。IPODや WALKMANとの相性も抜群ですので昔から最新のいい音楽(特に映画音楽)いい音が聴けますよ。
春休みぐらいをめどにオープンするつもりです。建具系はおむねできました。あとは陳列です。この準備はすごく楽しみなのですが、今から受験まで3月中旬ぐらいまで何も出来ないと思います。受験が落ち着けば、展示しながら絵本史、国内外の絵本作家・作品論を自分なりに研究しようと思っています・・・。営業時間は正午前ぐらいから、塾が始まる5時前ぐらいに閉店します。それからは塾生ら(ちょっとした休憩場所)と送迎の親御さんに開放します。
ああ・・・たくさん書き過ぎましたね。今後はIQ文庫について詳しくはこのリンク先に書いていこうと存じます。 ここまで読んでいただきありがとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。では、次回までごきげんよう!!
細野晴臣さんの『はらいそ』アニメはさくらももこさん。
どこか不思議な懐かしさと無国籍な異国情緒。こんな感じもいいよな・・。
2011年02月09日
世にも美しい数学入門
もう使わなくなった罫線入りのストックホーム用紙に数学の計算問題を解いている。熱中してやっているうちに、頭とは別に手先が勝手に計算しているような不思議な感覚に襲われることがある・・・。
手を休めてぼんやりしていると、数学に関していろんな考えをめぐらしている自分に気がつく。ピタゴラスの時代やそのずっと昔はこんな紙もペン、ましてやコンピューターもない時代にものすごい数学の発見・証明をしているひとたちがいたんだな~と。当時は利用できる数学定理(参考書)などもあまりなく、まさにゼロに近いかたちから自力で、いろんな数学的発見をしたのだな~と。その当時なら受験生は公式はすこししかおぼえなくてもいいかな~と。 今学生が苦労してやっている数学はみんな彼らが考え出したものの積み重ねなんだな~などなど・・・。
今学生が苦労してやっている数学はみんな彼らが考え出したものの積み重ねなんだな~などなど・・・。
そういえば数学者 藤原正彦さんと 作家小川洋子さん 対談『世にも美しい数学入門」のなかで藤原さんはもし宇宙人と対話できるとしたら、その共通言語は『数学』でしょう。数学は宇宙の法則を表現するものであり、まさにuniversalであると、言ってた。
うん、たしかにあの『はやぶさ』もちゃんと地球に計算どおり(苦労したけど)還って来たもんな~。
手を休めてぼんやりしていると、数学に関していろんな考えをめぐらしている自分に気がつく。ピタゴラスの時代やそのずっと昔はこんな紙もペン、ましてやコンピューターもない時代にものすごい数学の発見・証明をしているひとたちがいたんだな~と。当時は利用できる数学定理(参考書)などもあまりなく、まさにゼロに近いかたちから自力で、いろんな数学的発見をしたのだな~と。その当時なら受験生は公式はすこししかおぼえなくてもいいかな~と。
 今学生が苦労してやっている数学はみんな彼らが考え出したものの積み重ねなんだな~などなど・・・。
今学生が苦労してやっている数学はみんな彼らが考え出したものの積み重ねなんだな~などなど・・・。そういえば数学者 藤原正彦さんと 作家小川洋子さん 対談『世にも美しい数学入門」のなかで藤原さんはもし宇宙人と対話できるとしたら、その共通言語は『数学』でしょう。数学は宇宙の法則を表現するものであり、まさにuniversalであると、言ってた。
うん、たしかにあの『はやぶさ』もちゃんと地球に計算どおり(苦労したけど)還って来たもんな~。

2010年05月05日
端午の節句とたけくらべ
樋口一葉の『たけくらべ』(1895年1月 発表)を読んだのは遠い遠い昔のことだ。そのとき受けた感動は今でも忘れられない。リズムあるクラシカルな文体に魅了され、日本語のかな漢字混合文の素晴らしさに気づかされ、ここにほんとうに豊かな日本語がある、と感銘を受けた記憶がしっかりとある。
『たけくらべ』の舞台は廓の町、吉原。思春期の女の子と男の子たちの短い期間の成長の物語である。いずれ遊女となる水揚げまじかの美登利は勝気で自由闊達。そして美登利がひそかに恋心を抱く同じ学校の男子生徒はお寺の僧侶の息子、真如である。彼は、内気でクソ真面目の今で言うところの草食系男子。およそなにもかも正反対二人が互いに意識し合いながら、しかし、ぎこちない空気に気まずくなる。美登利は自らの運命と相手の身分の違いを分かっており、儚い恋と、心をいためる・・・。
一般に男子と女子では、女子の方が精神的成熟が早いと言われているが、うちの塾生はどうなんだろうか・・・。(まぁ、私などは同年代の女性には死ぬまで追いつけないだろうと、思っているけど・・・。) 総じて言えば、佇まい、授業態度、ものの言い方などは、やはり女子生徒が、きちんとしててずっと大人である。一方、話す内容は男子生徒は現状分析に関して鋭いことを言う、冷静である。結構、いろんなことにしっかり目を配っていたりしてるもんだな、と感心させられることもある。
男女差についてはバイオロジー的差異や社会制度の観点からいろいろ議論されている。英語の読解問題のテーマにもたまに登場する。しかし、ジェンダーフリーの観点からすれば、男子対女子の二項対立の構図でものごとを推し量るのは古い時代のステレオタイプと批判されるかもしれない・・・。
もし女性がいつか日か、国際政治勢力のマジョリティになったとすると(例:現代の政治リーダーの男女の比率がそのままひっくり返った世界。)その世界はどうなるだろうか?戦争・貧困は少なくなるのだろうか?まったく違う問題が新たに浮かび上がるだろうか?あんまり変わらないだろうか?
ああ、そうだ、今日は端午の節句、男の子の日なのだ。とにかく、男子よ、がんばれっ!

『たけくらべ』の舞台は廓の町、吉原。思春期の女の子と男の子たちの短い期間の成長の物語である。いずれ遊女となる水揚げまじかの美登利は勝気で自由闊達。そして美登利がひそかに恋心を抱く同じ学校の男子生徒はお寺の僧侶の息子、真如である。彼は、内気でクソ真面目の今で言うところの草食系男子。およそなにもかも正反対二人が互いに意識し合いながら、しかし、ぎこちない空気に気まずくなる。美登利は自らの運命と相手の身分の違いを分かっており、儚い恋と、心をいためる・・・。
一般に男子と女子では、女子の方が精神的成熟が早いと言われているが、うちの塾生はどうなんだろうか・・・。(まぁ、私などは同年代の女性には死ぬまで追いつけないだろうと、思っているけど・・・。) 総じて言えば、佇まい、授業態度、ものの言い方などは、やはり女子生徒が、きちんとしててずっと大人である。一方、話す内容は男子生徒は現状分析に関して鋭いことを言う、冷静である。結構、いろんなことにしっかり目を配っていたりしてるもんだな、と感心させられることもある。
男女差についてはバイオロジー的差異や社会制度の観点からいろいろ議論されている。英語の読解問題のテーマにもたまに登場する。しかし、ジェンダーフリーの観点からすれば、男子対女子の二項対立の構図でものごとを推し量るのは古い時代のステレオタイプと批判されるかもしれない・・・。
もし女性がいつか日か、国際政治勢力のマジョリティになったとすると(例:現代の政治リーダーの男女の比率がそのままひっくり返った世界。)その世界はどうなるだろうか?戦争・貧困は少なくなるのだろうか?まったく違う問題が新たに浮かび上がるだろうか?あんまり変わらないだろうか?
ああ、そうだ、今日は端午の節句、男の子の日なのだ。とにかく、男子よ、がんばれっ!

2010年03月29日
花見パーティ:賛成反対
最近車に乗っている間は『Cross-Cultural Seminar』という、英語学習者向けのCDをよく聴いています。そのCDでは、英語で日米の文化や価値観について、日本人の英語講師と日本在住のアメリカ人との間でいろいろな視点から話されています。アメリカ人のスーザンさんの話す英語はとても美しいです。(教養あるネイティヴスピーカーがかならずしも美しい英語を話すとは限りませんよね。)
実際、コチラで聴くことも出来ます。http://www.voicetrek.jp/index.html
そのなかのひとつのテーマ『花見』について、おもしろいディスカッションがありました。日本人講師は、今の『花見=パーティ』というあり方に反対し、一方アメリカ人の方が、擁護しています。
まず、日本人講師は、桜を見るために、シートで場所取りする行為は、ひどく自分勝手な行為だと批判しています。たとえば会社やサークルの新人にいい場所を陣取らせて、公共の場所を占拠するやり方は何の法的な正当性もない、と。アメリカ人は、まぁ、桜が咲く一時ぐらい『first come –first served 早いもの順』で、いいじゃありませんか、それでうまくいっているのだからと・・・。
また、日本人講師は、飲んだり食べたり、歌ったり、大騒ぎせずに、静かに桜を楽しみたい人の権利がない、と言うと、アメリカ人は、それはそうだけど、それぞれ、見知らぬ人同士であっても、一緒に盛り上がる楽しむあり方も好きですよ、といっています。
最後は、ごみを大量に置いて帰る人たちには、二人ともマナー違反と批判しつつ、いろんな人がバランスよく桜が楽しめればいいですね、と結んでいます。
この議論でおもしろいのは、日本人の方が、日本人の批判をし、外国の人が、それを理解したうえで日本人一般を擁護している点です。それによってうまいこと異文化を背景にしたもの同士意思相通ができているという・・・。
もちろん、日本では常識であるのものがアメリカで非常識であったり、その逆であったりすること、そしてそれぞれにそれなりの理由があるということも多く語られてて、面白いです。
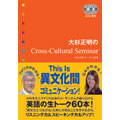
実際、コチラで聴くことも出来ます。http://www.voicetrek.jp/index.html
そのなかのひとつのテーマ『花見』について、おもしろいディスカッションがありました。日本人講師は、今の『花見=パーティ』というあり方に反対し、一方アメリカ人の方が、擁護しています。
まず、日本人講師は、桜を見るために、シートで場所取りする行為は、ひどく自分勝手な行為だと批判しています。たとえば会社やサークルの新人にいい場所を陣取らせて、公共の場所を占拠するやり方は何の法的な正当性もない、と。アメリカ人は、まぁ、桜が咲く一時ぐらい『first come –first served 早いもの順』で、いいじゃありませんか、それでうまくいっているのだからと・・・。
また、日本人講師は、飲んだり食べたり、歌ったり、大騒ぎせずに、静かに桜を楽しみたい人の権利がない、と言うと、アメリカ人は、それはそうだけど、それぞれ、見知らぬ人同士であっても、一緒に盛り上がる楽しむあり方も好きですよ、といっています。
最後は、ごみを大量に置いて帰る人たちには、二人ともマナー違反と批判しつつ、いろんな人がバランスよく桜が楽しめればいいですね、と結んでいます。
この議論でおもしろいのは、日本人の方が、日本人の批判をし、外国の人が、それを理解したうえで日本人一般を擁護している点です。それによってうまいこと異文化を背景にしたもの同士意思相通ができているという・・・。
もちろん、日本では常識であるのものがアメリカで非常識であったり、その逆であったりすること、そしてそれぞれにそれなりの理由があるということも多く語られてて、面白いです。
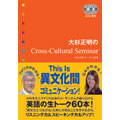
2009年11月05日
『ちょい大人力検定』
中学生の生徒さんと話していて、昔の自分とくらべることがあります。彼らはずいぶん大人です。いろんなことに気を使って生活しています。私の場合はもっと、幼稚というか、原始的だった気がします・・・。

カナダからの・・・ではなく、浦ノ崎港からです。
今の時代、昔に比べ、彼らは大人とおなじぐらい情報にさらされ、価値観は多様化し、人間関係もずっと複雑化しています。昔は先輩後輩・先生生徒・大人と子供・男子・女子の関係性がはっきりしていて、自分のポジションが分かりやすかった。今はそのような関係がすごくあいまいになっていますから、自分の立つ位置を見つけるためその場の空気を読むのが大事のようです。自由度が高まった分、いろいろ選択肢も増え、逆に大変なことも増えてしまったようです。これもまぁ、社会がより成熟してきた結果なのかな?と個人的には思っていますが・・・どうなのでしょう?

さて、『ちょい大人力検定』について。まず『大人力検定』というものがあって、社会生活のいろんな場面において、なすべき反応を選択して「大人度」を測るという検定試験形式の世渡り術本です。DSのソフトにもなっています。面白いです。『ちょい大人力検定』はそれの子供以上大人以下である14歳に向けのバージョンのものです簡単に言えば14歳というこの微妙な時期を上手にきりぬけるための処世術本です。『なんで、そんな若い時期に処世術を?サラリーマンじゃあるまいし。・・・』と言うご意見はごもっともです。しかし、生徒さんと話していると、彼らに他者と関わる(コミュニケーション)実践的技術をわかりやすく教える「マニュアル」もこの成熟した時代にあってもいいのじゃないかと思うのですが・・・。大人が読んでもおもしろいですし、彼らとコミュニケーションする上でも、参考になるかな?と思ってます。


カナダからの・・・ではなく、浦ノ崎港からです。
今の時代、昔に比べ、彼らは大人とおなじぐらい情報にさらされ、価値観は多様化し、人間関係もずっと複雑化しています。昔は先輩後輩・先生生徒・大人と子供・男子・女子の関係性がはっきりしていて、自分のポジションが分かりやすかった。今はそのような関係がすごくあいまいになっていますから、自分の立つ位置を見つけるためその場の空気を読むのが大事のようです。自由度が高まった分、いろいろ選択肢も増え、逆に大変なことも増えてしまったようです。これもまぁ、社会がより成熟してきた結果なのかな?と個人的には思っていますが・・・どうなのでしょう?

さて、『ちょい大人力検定』について。まず『大人力検定』というものがあって、社会生活のいろんな場面において、なすべき反応を選択して「大人度」を測るという検定試験形式の世渡り術本です。DSのソフトにもなっています。面白いです。『ちょい大人力検定』はそれの子供以上大人以下である14歳に向けのバージョンのものです簡単に言えば14歳というこの微妙な時期を上手にきりぬけるための処世術本です。『なんで、そんな若い時期に処世術を?サラリーマンじゃあるまいし。・・・』と言うご意見はごもっともです。しかし、生徒さんと話していると、彼らに他者と関わる(コミュニケーション)実践的技術をわかりやすく教える「マニュアル」もこの成熟した時代にあってもいいのじゃないかと思うのですが・・・。大人が読んでもおもしろいですし、彼らとコミュニケーションする上でも、参考になるかな?と思ってます。

2009年09月28日
『ドラゴン桜:センター対策編』
この漫画を読んで私はすっかりセンター試験モードです。センター試験まで残りわずか3ヶ月半ですし・・・

この漫画が徹底して描いてるのは、センター試験で出来るだけ効率よく多くの得点を得るための合理主義です・・・。
準備:今からセンターまでいかに合理的に取り組むか。
(世界史は後半から勉強すべし!出題率が高いから。)
本番;いかに合理的解くかのテクニック。
(文章問題そのものにヒントがある!問題作成者の立場から選択肢を絞れ!)
心得:試験までの心の持ちようと試験当日の心構え。
(本番の試験が終わった科目はすぐに答え合わせするな・話題にするな・耳を傾けるな!次の試験に頭を切り替えよ。)
東大を狙う登場人物と彼らを支える教師陣の取り組みをリアルに描かれています。
大学受験に関係ない社会人が読んでもいろいろためになることが描いてあると思いますよ。
いっきゅうに置いています。受験生に読んでもらうつもりです。

この漫画が徹底して描いてるのは、センター試験で出来るだけ効率よく多くの得点を得るための合理主義です・・・。
準備:今からセンターまでいかに合理的に取り組むか。
(世界史は後半から勉強すべし!出題率が高いから。)
本番;いかに合理的解くかのテクニック。
(文章問題そのものにヒントがある!問題作成者の立場から選択肢を絞れ!)
心得:試験までの心の持ちようと試験当日の心構え。
(本番の試験が終わった科目はすぐに答え合わせするな・話題にするな・耳を傾けるな!次の試験に頭を切り替えよ。)
東大を狙う登場人物と彼らを支える教師陣の取り組みをリアルに描かれています。
大学受験に関係ない社会人が読んでもいろいろためになることが描いてあると思いますよ。
いっきゅうに置いています。受験生に読んでもらうつもりです。
2009年09月08日
スヌーピー的生き方。
時代と国を超えて愛され続けている永遠のキャラクター。
大人も深~く味わえるスヌーピーの漫画。
『犬生?哲学』を教えてくれます。
『SNOOPYもっと気楽に』英文つき+和訳は谷川俊太郎
大人も深~く味わえるスヌーピーの漫画。
『犬生?哲学』を教えてくれます。
『SNOOPYもっと気楽に』英文つき+和訳は谷川俊太郎
2009年08月06日
『キャッチャーインザライ:ライ麦畑でつかまえて』
『蛍雪時代8月号』に夏休みに読むお奨め本が特集されています。テレビでおなじみの心理学者香山リカ先生は(今月号の特別講師)、『キャッチャーインザライ』を推薦されています。一般には『ライ麦畑でつかまえて』という邦題で知られるアメリカの小説です。お奨めの理由として、「高校生の『自分探しの物語』。『自分って何?』といろいろ思っているのは人には、ああ~自分と似たようなことを考えている高校生が昔も(1951年発表)いたんだ~、と知ってホッとする読み物だ」と。
『自分は、広いライ麦畑で遊んでいる子どもたちが、気付かずに崖っぷちから落ちそうになったときに、捕まえてあげるような、そんな人間になりたい。』主人公がたどり着いたひとつの結論です。
私は『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝訳)を大学生のとき読んでとても共感しました。確かに大学時代はワタシも『自分探しの旅』真っ最中だった気がします・・・。今もその旅は終わっていませんが・・・・(笑)。
主人公ホールデングは進学校の落ちこぼれ。でも喧嘩が強いワイルドな不良では決してなく(むしろ弱い。) 鬱陶しく、暗く、ひねくれて、自意識過剰・疎外感をもち・世の中は『嘘(lie)っぱちだらけ』だと思っている、今の日本でも何処にでもいるようなパッとしない青年なのです。(笑)でも、その『語り口』が非常に魅力的なのですね。感受性と言葉の表現力だけはすごくトンがってて、機知に富んで過激な言葉で世の中を切り込んでいきます。この辺をいかに訳するかがこの本の翻訳の醍醐味なのかもしれません。(The Catcher in the Rye 原書も是非読みたいです。)

この作品は『キャッチャーインザライ』というそのままのタイトルで村上春樹によって新しく訳されました。これは未読ですがその翻訳作業については『サリンジャー戦記』という文庫本で翻訳家、柴田元幸さんとの対談で詳しく述べられています。『翻訳』に関心あるワタシにとってもとても興味深い本でした。。

『自分は、広いライ麦畑で遊んでいる子どもたちが、気付かずに崖っぷちから落ちそうになったときに、捕まえてあげるような、そんな人間になりたい。』主人公がたどり着いたひとつの結論です。
私は『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝訳)を大学生のとき読んでとても共感しました。確かに大学時代はワタシも『自分探しの旅』真っ最中だった気がします・・・。今もその旅は終わっていませんが・・・・(笑)。
主人公ホールデングは進学校の落ちこぼれ。でも喧嘩が強いワイルドな不良では決してなく(むしろ弱い。) 鬱陶しく、暗く、ひねくれて、自意識過剰・疎外感をもち・世の中は『嘘(lie)っぱちだらけ』だと思っている、今の日本でも何処にでもいるようなパッとしない青年なのです。(笑)でも、その『語り口』が非常に魅力的なのですね。感受性と言葉の表現力だけはすごくトンがってて、機知に富んで過激な言葉で世の中を切り込んでいきます。この辺をいかに訳するかがこの本の翻訳の醍醐味なのかもしれません。(The Catcher in the Rye 原書も是非読みたいです。)

この作品は『キャッチャーインザライ』というそのままのタイトルで村上春樹によって新しく訳されました。これは未読ですがその翻訳作業については『サリンジャー戦記』という文庫本で翻訳家、柴田元幸さんとの対談で詳しく述べられています。『翻訳』に関心あるワタシにとってもとても興味深い本でした。。

2009年08月04日
『数学という最強の武器と渋滞学』
ドラゴン桜公式副読本『16歳の教科書2』を読んでいます。いろんな分野の第一線で活躍されとても個性的な人が講師となって、16歳へ向けておこなう模擬講座を集めたの本です。その講師のひとり西成活祐(かつひろ)さんの話は抜群におもしろいので、紹介します。
東大の宇宙工学の教授。高校時代、学校で使うテキストは買わず、授業では先生の声がジャマだということで耳栓して独学し(笑)、解けない問題があっても絶対模範解答は見ず、出来るまで一人で考えたと言う・・・。高校の先生にとってはなんとも憎っタラシイ生徒だったことでしょうね。(笑)

彼にとっては中高で教える「数学」は便宜的に「公式」をまる覚えしてパターン化した問題をその公式にそって解いていくものにすぎなかったのかもしれません。いちいち『公式』に対して、なぜなんだ?なぜそうなる?トコトンツッコンで来る生徒に対して『先生たち』はどこまで答えることが出来るのでしょうか?
西成少年の『なぜ?』にこだわった理由。それは『数学という最強の武器を手に入れたかったからだ。』そうです。『数学で証明されたものは、どんな相手だって、大統領だってNOと言えない。』と言う信念があったそうです。(英語に関してはワタシもそんな風にこだわっていたいとおもっています。)
東京大学の先生となった今、西成さんは数学は身近に具体的役に立っていると生徒には教えているそうです。例:ケータイ電話の画像伝送圧縮技術に中学で習う2次関数がつかわれている・・・。また、研究としての『渋滞学』と言うまったくあたらしい分野を開拓されました。
そのひとつの身近な例として『都会では混んでいる電車が来たら、やりすごして次の電車を待つほうが良い。』という法則です。なぜなら、たくさんの乗客が乗せている電車は乗客の乗降のとき時間がかかり遅れがちになるので、次の電車の到着時間の差は短くなる。しかも前の電車が乗客をたくさん乗せていった直後なので混んでない確率が高いし、乗り合わせするひとも少ない。というわけです。エレベータも同様らしいですよ。
『Jカーブ曲線の法則。』 どんな人にも波つまりスランプがある。下り坂をどんどん落っこちていく・・・でもなんとか頑張りぬいて底を抜けると、グーンと上昇する、という法則。目の前のことに一喜一憂することなく長期な視野で努力しているといつか大きな上昇気流が待っているということです。
ドラゴン桜こと桜木先生の招く講師陣の講義集はおもしろいです。当然ながら『16歳の教科書1』もあります。実は1の方が2より面白いと思います。以前読んでまして、ブログに書くつもりが書きそびれちゃったのです。それはいずれまた・・・。
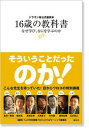
東大の宇宙工学の教授。高校時代、学校で使うテキストは買わず、授業では先生の声がジャマだということで耳栓して独学し(笑)、解けない問題があっても絶対模範解答は見ず、出来るまで一人で考えたと言う・・・。高校の先生にとってはなんとも憎っタラシイ生徒だったことでしょうね。(笑)

彼にとっては中高で教える「数学」は便宜的に「公式」をまる覚えしてパターン化した問題をその公式にそって解いていくものにすぎなかったのかもしれません。いちいち『公式』に対して、なぜなんだ?なぜそうなる?トコトンツッコンで来る生徒に対して『先生たち』はどこまで答えることが出来るのでしょうか?
西成少年の『なぜ?』にこだわった理由。それは『数学という最強の武器を手に入れたかったからだ。』そうです。『数学で証明されたものは、どんな相手だって、大統領だってNOと言えない。』と言う信念があったそうです。(英語に関してはワタシもそんな風にこだわっていたいとおもっています。)
東京大学の先生となった今、西成さんは数学は身近に具体的役に立っていると生徒には教えているそうです。例:ケータイ電話の画像伝送圧縮技術に中学で習う2次関数がつかわれている・・・。また、研究としての『渋滞学』と言うまったくあたらしい分野を開拓されました。
そのひとつの身近な例として『都会では混んでいる電車が来たら、やりすごして次の電車を待つほうが良い。』という法則です。なぜなら、たくさんの乗客が乗せている電車は乗客の乗降のとき時間がかかり遅れがちになるので、次の電車の到着時間の差は短くなる。しかも前の電車が乗客をたくさん乗せていった直後なので混んでない確率が高いし、乗り合わせするひとも少ない。というわけです。エレベータも同様らしいですよ。
『Jカーブ曲線の法則。』 どんな人にも波つまりスランプがある。下り坂をどんどん落っこちていく・・・でもなんとか頑張りぬいて底を抜けると、グーンと上昇する、という法則。目の前のことに一喜一憂することなく長期な視野で努力しているといつか大きな上昇気流が待っているということです。
ドラゴン桜こと桜木先生の招く講師陣の講義集はおもしろいです。当然ながら『16歳の教科書1』もあります。実は1の方が2より面白いと思います。以前読んでまして、ブログに書くつもりが書きそびれちゃったのです。それはいずれまた・・・。
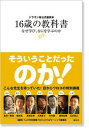
2009年06月20日
派遣村と13歳のハローワーク
昨日の報道ステーションで、派遣村の村長・湯浅誠さんが出演されていました。
いま、多くの若者には非正規雇用形の仕事しかない。彼らは景気循環や企業の都合で、いいように雇われたり、解雇されたり不安定な雇用状況下にいる。当然将来が不安なので、お金を使わない・使えない。家庭も持たない。その消費が回らない。その結果企業業績が悪くなり、雇用状況が悪くなる。政府も税収が減り、社会保障費の財源がなくなる・・・。日本社会は「貧困のスパイラル」状態に陥りつつあるんだと言っています。

今、教えている生徒さんが働き出すであろう5・6・7・・年先の日本はどうなっているのだうか?と考えるときがあります。そして、そんなことを生徒さんと話したりします。彼らに、村上龍「13歳のハローワーク」を見せています。大まかでもいいから早い時期に自分の将来の職業について考えること。若くして汎用性がありかつ専門的な仕事ができるようになっていること。そのために早目に準備しておくこと。今の時代、それも必要なのかな?と考えます。進むべき大学・学部も「ソコ」から逆算される。すると目標がはっきりして勉強する意味が具体化し勉強の姿勢も違ってくると考えます。
今教えていることが本当に生徒さんたちの将来役に立つのだろうか?役に立ってほしいと願いながらいつも教えています。
いま、多くの若者には非正規雇用形の仕事しかない。彼らは景気循環や企業の都合で、いいように雇われたり、解雇されたり不安定な雇用状況下にいる。当然将来が不安なので、お金を使わない・使えない。家庭も持たない。その消費が回らない。その結果企業業績が悪くなり、雇用状況が悪くなる。政府も税収が減り、社会保障費の財源がなくなる・・・。日本社会は「貧困のスパイラル」状態に陥りつつあるんだと言っています。

今、教えている生徒さんが働き出すであろう5・6・7・・年先の日本はどうなっているのだうか?と考えるときがあります。そして、そんなことを生徒さんと話したりします。彼らに、村上龍「13歳のハローワーク」を見せています。大まかでもいいから早い時期に自分の将来の職業について考えること。若くして汎用性がありかつ専門的な仕事ができるようになっていること。そのために早目に準備しておくこと。今の時代、それも必要なのかな?と考えます。進むべき大学・学部も「ソコ」から逆算される。すると目標がはっきりして勉強する意味が具体化し勉強の姿勢も違ってくると考えます。
今教えていることが本当に生徒さんたちの将来役に立つのだろうか?役に立ってほしいと願いながらいつも教えています。
2009年06月03日
『バカの壁』と説明力
今、児童英語の教授法を勉強しているのですが、『教えることの』本質がそこにあるようにおもいます。英語以前に、日本語でさえものごとをよく分からないってない児童に英語で英語を説明する、ということ。まさに柄谷行人が言う『共通の規則を有しない他者に外国語を教える』ということです。・・・児童英語でつかう教える技術はすべての教える技術に通ずるものがあると思います。
教えることでとても重要なスキルのひとつは『説明する力』だと思います。いかに分かりやすく説明できるか。説明する力に付随するスキルは「描写力」です。いきいきと場面を再現できる力。「表現力」とも言い換えてもいいでしょう。上手に言い換える豊富な語彙力。具体例の出し方。たとえ話がうまいこと。さらに、複雑な話や言葉をきれいにまとめる「要約力」 そして、話の盛り上げ方、展開がうまい「構成力」 文脈・言葉の裏に潜むメッセージを読み取る「洞察力」・・・などが、上手に説明できるための重要なスキルだと思います。
養老孟司さんは話題になった本『バカの壁』の中で、バカの壁のひとつに『分かっているつもりでいること。』をあげてます。例としてほとんどの男子医学生が女性の「出産」のことを分かっている(学問を通して)つもりになっているが本当に女性が「出産」するときの心理・肉体的負担など分かっちゃない、いやむしろ、分かろうとしない・分かりたくないのだ。と、言っています。・ ・・そこに『バカの壁』があるのだと書いています。

そしてそういう『分かったつもりの大学生』にかぎって何か分からない時は『先生、説明くしてださい。』と訪ねてくるそうです。世の中には『説明できないものがあると知ること。』もたいせつなのだと書いています。大学生ともなると、そういうことも知っておくべきなのですね・・・
でも考えてみると『何かを説明できない』と言う前に、ものごとをキチンと説明できる
スキルを持つ人間でないとそれが『説明できない。』とは言えないと思うのです。まさに、この文庫本のカバーに書いてあるとおり、『いつの間にか私たちの前には様々な「壁」に囲まれている。それを知ることで気が楽になる。世界の見方が分かってくる。』と。つまり、『「バカの壁=囲われた世界にのみ通用する知識・知恵」を乗り越えるにはその壁の存在知らなくてはいけない』すなわち『説明できないものを知る=「壁」があることを知る』には『きちん説明できる技術をもつ。』ことだと思うのです。

玄海町 X-PROCESSED
『世に中には説明できないものがあるんだよ・・・。』そのぐらい言えるよう、ワタシはもっともっと『上手に説明できる技術』を身につけていこう、とおもう次第なのです。
教えることでとても重要なスキルのひとつは『説明する力』だと思います。いかに分かりやすく説明できるか。説明する力に付随するスキルは「描写力」です。いきいきと場面を再現できる力。「表現力」とも言い換えてもいいでしょう。上手に言い換える豊富な語彙力。具体例の出し方。たとえ話がうまいこと。さらに、複雑な話や言葉をきれいにまとめる「要約力」 そして、話の盛り上げ方、展開がうまい「構成力」 文脈・言葉の裏に潜むメッセージを読み取る「洞察力」・・・などが、上手に説明できるための重要なスキルだと思います。
養老孟司さんは話題になった本『バカの壁』の中で、バカの壁のひとつに『分かっているつもりでいること。』をあげてます。例としてほとんどの男子医学生が女性の「出産」のことを分かっている(学問を通して)つもりになっているが本当に女性が「出産」するときの心理・肉体的負担など分かっちゃない、いやむしろ、分かろうとしない・分かりたくないのだ。と、言っています。・ ・・そこに『バカの壁』があるのだと書いています。

そしてそういう『分かったつもりの大学生』にかぎって何か分からない時は『先生、説明くしてださい。』と訪ねてくるそうです。世の中には『説明できないものがあると知ること。』もたいせつなのだと書いています。大学生ともなると、そういうことも知っておくべきなのですね・・・
でも考えてみると『何かを説明できない』と言う前に、ものごとをキチンと説明できる
スキルを持つ人間でないとそれが『説明できない。』とは言えないと思うのです。まさに、この文庫本のカバーに書いてあるとおり、『いつの間にか私たちの前には様々な「壁」に囲まれている。それを知ることで気が楽になる。世界の見方が分かってくる。』と。つまり、『「バカの壁=囲われた世界にのみ通用する知識・知恵」を乗り越えるにはその壁の存在知らなくてはいけない』すなわち『説明できないものを知る=「壁」があることを知る』には『きちん説明できる技術をもつ。』ことだと思うのです。
玄海町 X-PROCESSED
『世に中には説明できないものがあるんだよ・・・。』そのぐらい言えるよう、ワタシはもっともっと『上手に説明できる技術』を身につけていこう、とおもう次第なのです。
2009年06月01日
『探究』教えることについて。
思想家・柄谷行人は『探究』(半分も理解できたかな?w)で『教えることの奇跡』を語っています。『教えるとは子供に言葉を教えること、あるいは外国人に言葉を教えること。いいかえれば、私の言葉をまったく知らない者にそれを教えこむこと:ウィドゲンシュタインより』もし、教える立場のものが、『彼・私にあてはまることは誰にでもあてはまる』と思ったり、『教える側と教えられる側が対称である。』と考えてるのであれば、それは教えてるのではなく『ひとりごと』にすぎない、と。

例えば 自転車・水泳を子供に教えようとするとき、教えるほうはあれやこれやと彼らに言って試行錯誤をさせますよね。で、いつまにか出来るようになります。でも、どの方法が彼らに良かったのかは後からでないと分かりません。また、どんな子供でもかならず『泳げる』『自転車にのれる』ようになる普遍的法則というものはありませんね。つまり、万人に当てはまるような『教え方』はない。あるとすれば常に後付によるものです。(絶対ある!と主張するものは『ひとりごと』を言ってるにすぎない。)実際はその場、その場の一回限りの『命がけの飛躍』の連続なのだと・・・。
確かに世間一般に語られてる『良い教え方』はあるのでしょう。でもそれをそのとおりやったらかといって、『教えられる側』がすべてできるようになる訳ではありません。『教えることが成果』を生むのはけっきょく教わる側に決定権を握られておりまして教えるものの立場は常に弱いのです・・・。(非対称性)

x-processed lomography ふくおかマリナシティ
ワタシ自信も以前は同じことを同じように教えても、どんどんできる生徒さんがいる一方で、できるまで時間がかかる生徒さんがいることに、どうしてなんだろう?と考えこんでいました。しかし、生徒さんひとりひとり個性や事情がちがうので『一概にコレをやったら大丈夫だ!』と決め付けられない、と当たり前なことに気がついたのです。
【宣伝です。(=^・^=)】
いっきゅうは個別塾です。それぞれの生徒さん個性・能力にあわせて、教え方。カリキュラムを変えて個別に授業を行います。
『出来る生徒さん』
全国進学レベルを見据えてどんどん先へと進めています。ある中1の生徒は、中間テスト英語・数学(中学数学対応してます。)とも満点でした。そのような生徒さんは、学校の授業のペースが遅すぎると感じるようです。また、出来る中学3年生には高校英文法を教えています。そうすることで、さらに上級の読解や英作文にいち早く取り組めるからです。
『逆に時間がかかる生徒さん』
英語や数学は積み重ねが大事ですので、じっくりと、基本から固めて行きます。なぜ苦手なのか?苦手な部分はどこなのか、詳細に分析して対策を講じてゆきます。伸びる時期は個人差があります。重要なのはその時期を見逃さない。そしてそれまでの、種撒き、耕作、水撒きを怠らない、ことだと思います。(基本的学力としての計算力・国語力・論理的思考を持つ。)

例えば 自転車・水泳を子供に教えようとするとき、教えるほうはあれやこれやと彼らに言って試行錯誤をさせますよね。で、いつまにか出来るようになります。でも、どの方法が彼らに良かったのかは後からでないと分かりません。また、どんな子供でもかならず『泳げる』『自転車にのれる』ようになる普遍的法則というものはありませんね。つまり、万人に当てはまるような『教え方』はない。あるとすれば常に後付によるものです。(絶対ある!と主張するものは『ひとりごと』を言ってるにすぎない。)実際はその場、その場の一回限りの『命がけの飛躍』の連続なのだと・・・。
確かに世間一般に語られてる『良い教え方』はあるのでしょう。でもそれをそのとおりやったらかといって、『教えられる側』がすべてできるようになる訳ではありません。『教えることが成果』を生むのはけっきょく教わる側に決定権を握られておりまして教えるものの立場は常に弱いのです・・・。(非対称性)
x-processed lomography ふくおかマリナシティ
ワタシ自信も以前は同じことを同じように教えても、どんどんできる生徒さんがいる一方で、できるまで時間がかかる生徒さんがいることに、どうしてなんだろう?と考えこんでいました。しかし、生徒さんひとりひとり個性や事情がちがうので『一概にコレをやったら大丈夫だ!』と決め付けられない、と当たり前なことに気がついたのです。
【宣伝です。(=^・^=)】
いっきゅうは個別塾です。それぞれの生徒さん個性・能力にあわせて、教え方。カリキュラムを変えて個別に授業を行います。
『出来る生徒さん』
全国進学レベルを見据えてどんどん先へと進めています。ある中1の生徒は、中間テスト英語・数学(中学数学対応してます。)とも満点でした。そのような生徒さんは、学校の授業のペースが遅すぎると感じるようです。また、出来る中学3年生には高校英文法を教えています。そうすることで、さらに上級の読解や英作文にいち早く取り組めるからです。
『逆に時間がかかる生徒さん』
英語や数学は積み重ねが大事ですので、じっくりと、基本から固めて行きます。なぜ苦手なのか?苦手な部分はどこなのか、詳細に分析して対策を講じてゆきます。伸びる時期は個人差があります。重要なのはその時期を見逃さない。そしてそれまでの、種撒き、耕作、水撒きを怠らない、ことだと思います。(基本的学力としての計算力・国語力・論理的思考を持つ。)





