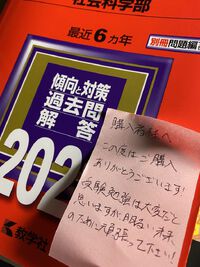2013年06月03日
高1の数学風景
毎年この時期、新・高校一年生は、多かれ少なかれ、高校数学に圧倒されまくってる気がします。すくなくとも当塾では今まではそうでしたし、今年もそうです。彼・彼女らは決して中学では数学が苦手ではなく、いやむしろ出来ていた方なのですが・・・はて、どうしてだろう?
いろいろ意見を聞いてみると、授業のペースが早い。教科書があまりにもぶっきらぼう。宿題多い。 また内容としては、よく分からない文字が出てき、場合分けを一々しなくちゃならなかったり、一生懸命計算した結果、『解なし』あるいは『すべての実数』であったり、と、中学の数学からするとすっきり正解が出なくて気持ちが良くないと口を揃えます・・・・。
また内容としては、よく分からない文字が出てき、場合分けを一々しなくちゃならなかったり、一生懸命計算した結果、『解なし』あるいは『すべての実数』であったり、と、中学の数学からするとすっきり正解が出なくて気持ちが良くないと口を揃えます・・・・。 要するにこれまで学んできた数学風景ががらりと変わってしまい違和感を覚えているようです。ふむむ・・・。
要するにこれまで学んできた数学風景ががらりと変わってしまい違和感を覚えているようです。ふむむ・・・。
中学の数学はある意味、取り扱う範囲がセーフティネットの囲いの中で限定的に勉強して来たのだといえるのかもしれません。しかも走るべきトラックがあらかじめ示されているような・・・。(直線的に解いていけばかならずひとつの正解にたどり着くように仕組まれてある。)高校数学ははそのネットがかなり拡張されて、扱うその数がいったいどういう範疇のものであるか、常に意識しなきゃならないわけです・・・。
でも、この山をガンバってどうにか乗り越えると、これから学んでゆく高校数学の光景がさっ~と拡がります。その光景とはこれから越えるべきいくつもの山々です。どれも平坦なものはありませんが、山をひとつひとつ超えてゆくたびにさらに新しい数学の風景が開けててゆきます。私は彼・彼女らの良きシェルパ役でありたいと考えています。
さて、前置きが長くなりましたが、南みやこ著「『なぜ?どうして』をとことん考える高校数学」という本は参考になります。著者は立派な論文を書かれた数学者であり教師であるが、その高校時代はけっして他の生徒と比べて数学が出来たわけでもなく、むしろ、違和感とぎこちなさを常に感じていたそうです。
著者はなんでもいちいち突き詰める性格で、疑問があるとそれが分かるまで前に進めない性格の女子高生だったようです。近頃のように分かりやすい参考書や進学塾もあまり一般的でない時代、女子高生ひとりが、ぶっきらぼうな教科書を片手に、数学的ひらめき派の男子生徒を尻目にいかに高校数学に立ち向かったか、回想録のように語ってゆきます。面白いですよ。

じゃあまたね~。
いろいろ意見を聞いてみると、授業のペースが早い。教科書があまりにもぶっきらぼう。宿題多い。
 また内容としては、よく分からない文字が出てき、場合分けを一々しなくちゃならなかったり、一生懸命計算した結果、『解なし』あるいは『すべての実数』であったり、と、中学の数学からするとすっきり正解が出なくて気持ちが良くないと口を揃えます・・・・。
また内容としては、よく分からない文字が出てき、場合分けを一々しなくちゃならなかったり、一生懸命計算した結果、『解なし』あるいは『すべての実数』であったり、と、中学の数学からするとすっきり正解が出なくて気持ちが良くないと口を揃えます・・・・。 要するにこれまで学んできた数学風景ががらりと変わってしまい違和感を覚えているようです。ふむむ・・・。
要するにこれまで学んできた数学風景ががらりと変わってしまい違和感を覚えているようです。ふむむ・・・。中学の数学はある意味、取り扱う範囲がセーフティネットの囲いの中で限定的に勉強して来たのだといえるのかもしれません。しかも走るべきトラックがあらかじめ示されているような・・・。(直線的に解いていけばかならずひとつの正解にたどり着くように仕組まれてある。)高校数学ははそのネットがかなり拡張されて、扱うその数がいったいどういう範疇のものであるか、常に意識しなきゃならないわけです・・・。
でも、この山をガンバってどうにか乗り越えると、これから学んでゆく高校数学の光景がさっ~と拡がります。その光景とはこれから越えるべきいくつもの山々です。どれも平坦なものはありませんが、山をひとつひとつ超えてゆくたびにさらに新しい数学の風景が開けててゆきます。私は彼・彼女らの良きシェルパ役でありたいと考えています。

さて、前置きが長くなりましたが、南みやこ著「『なぜ?どうして』をとことん考える高校数学」という本は参考になります。著者は立派な論文を書かれた数学者であり教師であるが、その高校時代はけっして他の生徒と比べて数学が出来たわけでもなく、むしろ、違和感とぎこちなさを常に感じていたそうです。
著者はなんでもいちいち突き詰める性格で、疑問があるとそれが分かるまで前に進めない性格の女子高生だったようです。近頃のように分かりやすい参考書や進学塾もあまり一般的でない時代、女子高生ひとりが、ぶっきらぼうな教科書を片手に、数学的ひらめき派の男子生徒を尻目にいかに高校数学に立ち向かったか、回想録のように語ってゆきます。面白いですよ。

じゃあまたね~。